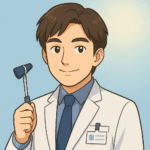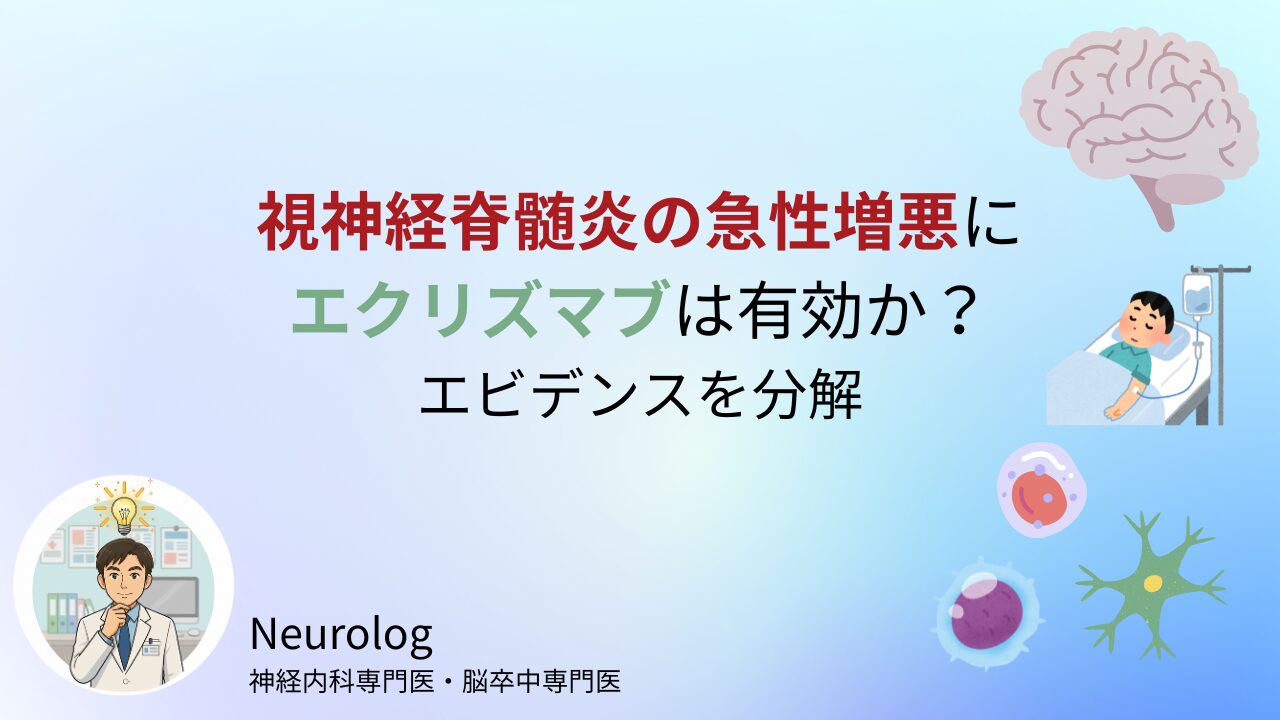多発性硬化症(MS)患者は脳卒中リスクが高いのか?―2025年の人口ベース大規模コホートを実践的に読み解く―
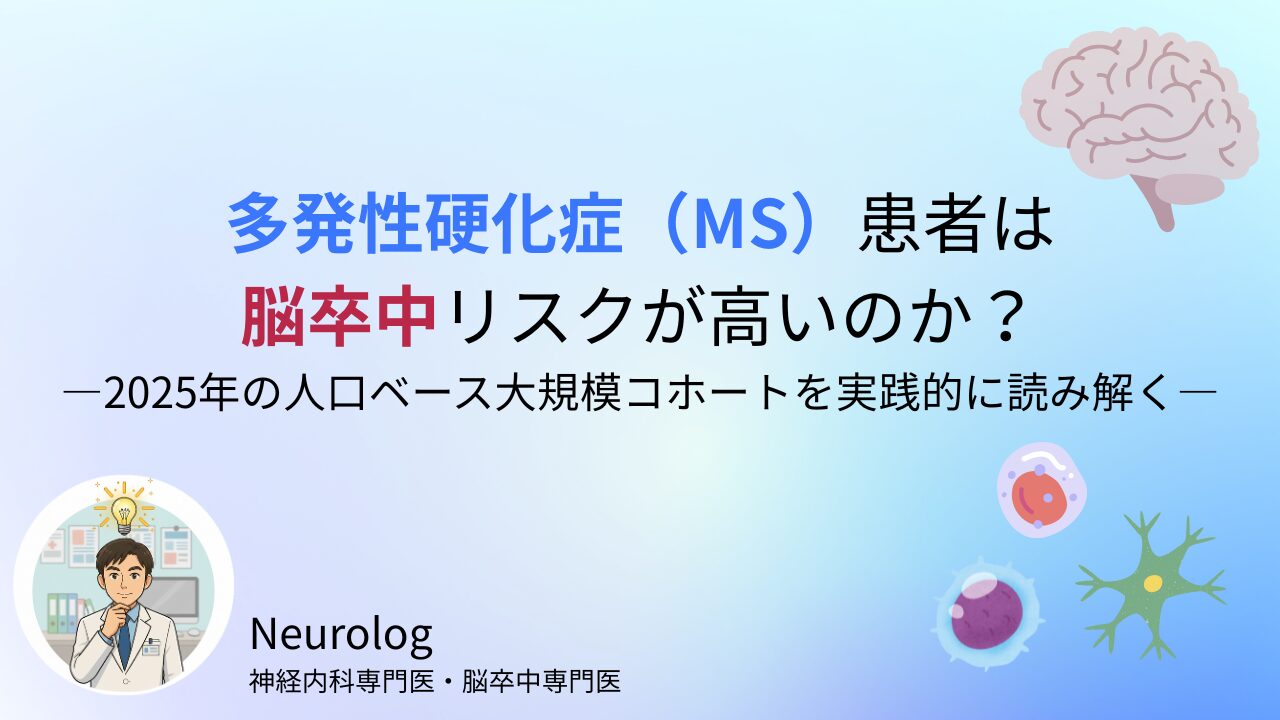
はじめに:Clinical Question(CQ)
CQ: 多発性硬化症(Multiple Sclerosis: MS)患者は、一般集団と比べて脳卒中(虚血性・脳出血を含む)リスクが増加するのでしょうか?
この問いは、MS患者さんの長期的な健康管理を考える上で非常に重要です。
これまでいくつかの研究でMSと脳卒中リスクの関連が示唆されてきましたが、研究デザインによる結果のばらつきが大きいのが実情でした。
本記事では、この臨床的疑問に答えるため、医学雑誌 Multiple Sclerosis and Related Disorders に掲載された2025年の大規模な人口ベース後ろ向きコホート研究(Yahav A, et al.)を深掘りします。
この論文の重要な結論は「MSと脳卒中リスクの増加に有意な関連はない」というものです。
しかし、なぜ過去の研究、特にメタ解析では「リスクは増加する」と報告されていたのでしょうか?
この記事では、研究デザインや交絡調整といった疫学的な視点からこの最新論文を実践的に読み解き、明日からの臨床にどう活かすべきかを解説します。
研究の要点(Yahav 2025, MSARD)
まずは、今回取り上げる研究の概要をPICO(Patient, Intervention/Exposure, Comparison, Outcome)に沿って整理します。
PICO(Patient, Intervention/Exposure, Comparison, Outcome)
- P (Patient): 25歳以上の新規MS患者(n=1,602)
- I/E (Intervention/Exposure): MSの診断
- C (Comparison): 年齢・性別・人口セクターで10:1にマッチングした非MS対照群(n=16,020)
- O (Outcome): 全脳卒中、虚血性脳卒中、脳出血の発症(ICD-9コードで同定)
💡 PICOとは? 臨床研究の論文を読む際に、その骨格(目的)を明確にするためのフレームワークです。
「どのような患者さん(P)に、何の要因(I/E)が、何と比べて(C)、どのような結果(O)をもたらしたか」を整理することで、研究の結論を素早く正確に理解できます。
研究の概要
- デザイン/データベース: イスラエル最大の医療保険機関である Clalit Health Services (CHS) のデータベースを用いた、人口ベースの後ろ向きコホート研究です。
- 対象者: 2005年1月1日から2022年12月31日までに新たにMSと診断された25歳以上の患者さん(1,602名)と、年齢・性別などを厳密にマッチさせた非MSの対照群(16,020名)、合計17,622名が対象です。
- 追跡期間: MS診断日から2023年12月31日まで追跡し、初回の脳卒中発症を評価しました。
- 主要アウトカム: 全脳卒中、虚血性脳卒中、脳出血の発症。診断は国際疾病分類第9版(International Classification of Diseases, Ninth Revision: ICD-9)コードに基づいています。
主な結果
- 総追跡期間182,156人年において、259件の脳卒中が確認されました。
- 脳卒中の粗発症率は、MS群で1.61/1,000人年、非MS群で1.40/1,000人年でした。
- しかし、高血圧や糖尿病などの血管リスク因子を統計的に調整した後の調整ハザード比 (adjusted Hazard Ratio: aHR) は以下の通りで、いずれも統計的な有意差は認められませんでした。
- 全脳卒中: aHR 0.95 (95%信頼区間[CI] 0.61–1.48)
- 虚血性脳卒中: aHR 0.94 (95% CI 0.59–1.51)
- 脳出血: aHR 0.94 (95% CI 0.25–3.56)
- 脳卒中既往歴のある患者を除外したり、追跡期間を2年間に限定したりする感度分析でも、結果は一貫していました。
実臨床への落とし込み
この研究が示す最も重要なメッセージは、「MSであること自体が、独立した脳卒中の危険因子とは言えない可能性が高い」ということです。
したがって、MS患者さんの脳卒中予防戦略は、一般集団と同様に、高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙といった古典的な血管リスク因子を愚直に管理することが基本となります。
なぜ先行研究と結論が違うのか?
(メタ解析 vs 近年の大規模調整研究)
では、なぜ2019年に報告されたメタ解析(BMC Neurology)などでは、「MSは脳卒中リスクを増加させる(1年でRR 3.48, 10年超でRR 2.45)」と結論付けられていたのでしょうか。
Yahavらの研究との違いは、主に交絡因子の調整の精度にあると考えられます。
- 交絡因子の扱い:
MS患者さんは、運動不足や喫煙率の高さ、あるいは治療薬(ステロイドなど)の影響で、高血圧や糖尿病といった血管リスク因子を併存しやすい傾向があります。
過去の研究では、これらの交絡因子が十分に調整されていなかったため、MSと脳卒中が見かけ上関連しているように見えた可能性があります。
Yahavらの研究では、多変量Cox比例ハザードモデルを用いて、広範な心血管リスク因子や薬剤使用の有無を詳細に調整しており、その結果、関連が消失しました。
🔎 交絡因子とは?
調べたい原因(例:MS)と結果(例:脳卒中)の両方に関係し、見かけ上のウソの関連を作り出してしまう第三の因子のことです。 例えば、「喫煙」はMS患者さんで多い傾向があり、かつ脳卒中の直接の原因でもあります。もし「喫煙」を考慮せずに分析すると、MSが脳卒中の原因であるかのように誤って結論付けてしまう可能性があります。
- 診断コードの妥当性:
行政データベースを用いた研究では、ICDコードの診断精度が結果に影響します。
一般的に、脳出血の診断コードは陽性的中率 (Positive Predictive Value: PPV) が高い一方、虚血性脳卒中はコードによって精度にばらつきがあることが知られています(PPV 70–90%程度)。研究間で診断精度が異なれば、結果にもばらつき(異質性)が生じます。過去のメタ解析で異質性が高かった一因と考えられます。
🔎 陽性的中率 (PPV) とは?
ある診断コードで「脳卒中」と記録された人のうち、本当に脳卒中であった人の割合のことです。「診断コードの的中率」と考えると分かりやすいです。
研究手法(Research Method)の吟味
(因果推論の視点)
この研究の質をさらに深く評価してみましょう。
- 選択バイアス: CHSはイスラエル人口の半数以上をカバーする巨大データベースであり、対象者の代表性が高く、選択バイアスは小さいと考えられます。結果の一般化可能性は、同様の公的医療保険制度を持つ先進国において妥当性が高いでしょう。
- 測定バイアス(情報バイアス): アウトカム(脳卒中)の同定をICD-9コードに依存している点は、この種の研究の限界です。しかし、感度分析でも結果が揺るがないことから、結論の頑健性は高いと評価できます。
- 残余交絡: どれだけ多くの因子を調整しても、測定されていない交絡因子が結果に影響を与える可能性は常に残ります。例えば、食事や身体活動量、MSの重症度、あるいは疾患修飾薬(Disease-Modifying Therapy: DMT)の種類別の影響などは、この研究では十分に評価できていません。
したがって、「MSは脳卒中リスクを全く増加させない」と断言するのではなく、「現時点での質の高い大規模データでは、独立したリスク増加は否定的である」という、慎重かつ妥当な解釈が求められます。
🔎 感度分析とは?
「分析の条件を少し変えても(例:脳卒中の既往がある人を除く、など)、同じような結果が得られるか?」を確認する追加の分析です。これを行っても結論が変わらなければ、その結果は信頼できる(頑健である)と言えます。
Take-home Message
この研究結果を踏まえ、私たちは臨床現場でどう行動すべきでしょうか。
結論の一言:MSだからといって脳卒中を過度に恐れる必要はない。個々の患者さんが持つ一般的な血管リスクの管理が最優先。
MS患者に対してやるべきこと
- 標準的な二次予防の徹底: 血圧(目標 < 130/80 mmHg)、脂質、血糖の管理、そして禁煙指導。これらをMSの診療と並行して、抜かりなく行うことが重要です。睡眠時無呼吸症候群など、見逃されがちなリスク因子にも注意を払いましょう。
- MS治療薬への個別対応: DMTや急性増悪時のステロイドパルス療法が、短期的に血圧や血糖に影響を与える可能性があります。治療中はこれらのバイタルサインをモニタリングし、必要に応じて介入します。
- 鑑別診断の意識: MS患者さんの一過性神経症状を診る際には、常に「再発(relapse)」なのか「一過性脳虚血発作(Transient Ischemic Attack: TIA)」なのかを意識します。年齢、発症様式、症状、持続時間、過去のMRI所見との比較などを参考に、丁寧な鑑別が求められます。
患者さんへの説明例
「最近の大規模な研究で、多発性硬化症だからといって、脳卒中のリスクが特別に高くなるわけではない、ということが分かってきました。それよりも、血圧やコレステロール、喫煙といった、一般的な生活習慣病の対策をしっかり行うことが、将来の脳卒中を防ぐ上で一番大切です。」
研究の限界と今後の課題
本研究は非常に有益ですが、若年発症のMS患者や疾患活動性が高い患者におけるリスク、あるいはDMTの種類による影響といった、より詳細なサブグループでの解析が今後の課題です。
また、国や人種、医療制度の違いを超える普遍的な結論を得るためには、さらなる追跡研究が期待されます。
よくある疑問(FAQ)
Q1. 海外の研究結果ですが、日本人のMS患者さんにもそのまま当てはまりますか?
A1. MSの基本的な病態は人種を超えて普遍的ですが、背景となる血管リスク因子の分布や医療制度、ICDコーディングの慣行が異なるため、リスクの大きさが完全に同じとは限りません。しかし、「一般的な血管リスク管理が重要」という本質的なメッセージは、日本人患者さんにも普遍的に当てはまると考えてよいでしょう。
Q2. MSの再発(急性増悪)とTIAの区別が難しいことがあると聞きます。これが過去の研究結果に影響した可能性はありますか?
A2. その可能性は十分に考えられます。特にデータベース研究では、臨床情報が限られるため、MSの再発による神経症状がTIAとして誤ってコードされたケースが含まれていたかもしれません。これが、過去の研究でMSと脳卒中の関連が過大評価された一因である可能性が指摘されています。臨床での基本は、「超急性発症で短時間ならTIA」「亜急性発症で24時間以上続くならMS再発」です。さらに、症状の分布や内容(陰性症状中心か、陽性症状を伴うか)や患者さんの年齢・背景リスクを考慮し、最終的にはMRIで確定診断に至るという流れが重要です。
まとめ
2025年に報告されたイスラエルの大規模コホート研究では、多発性硬化症(MS)であること自体は、脳卒中リスクの独立した増加因子ではないことが示唆されました。過去にリスク増加を報告した研究は、交絡因子の調整不足や診断精度の問題があった可能性があります。
臨床的には、MS患者さんの脳卒中予防として、一般的な血管リスク(高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙など)の管理を徹底するという王道のアプローチが最も重要です。
参考文献
- Yahav A, Ryan D, Golan D, et al. Association between multiple sclerosis and the risk of stroke: A population-based retrospective cohort study. Mult Scler Relat Disord. Published online September 1, 2025. doi:10.1016/j.msard.2025.106715
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40929925/ - Hong Y, Tang HR, Ma M, Chen N, Xie X, He L. Multiple sclerosis and stroke: a systematic review and meta-analysis. BMC Neurol. 2019;19(1):139. Published 2019 Jun 24. doi:10.1186/s12883-019-1366-7
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31234793/ - Orso M, Cozzolino F, Amici S, et al. Validity of cerebrovascular ICD-9-CM codes in healthcare administrative databases. The Umbria Data-Value Project. PLoS One. 2020;15(1):e0227653. Published 2020 Jan 9. doi:10.1371/journal.pone.0227653
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31918434/