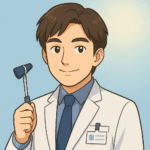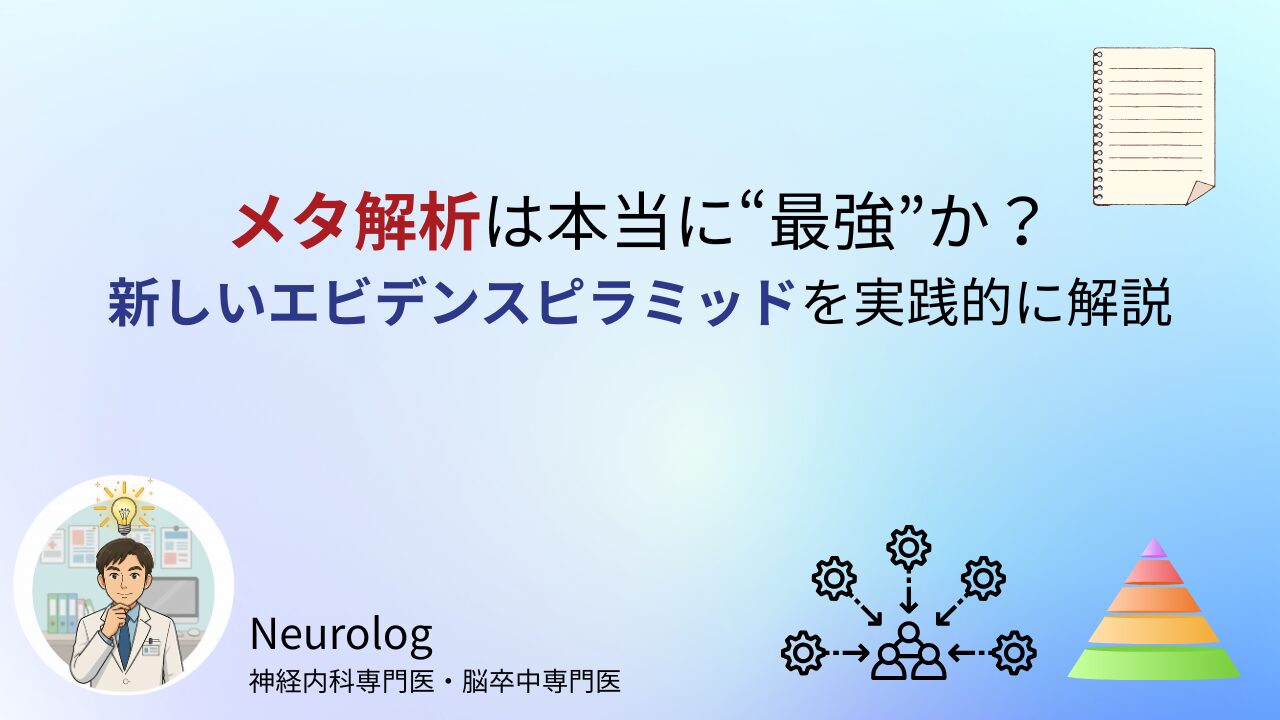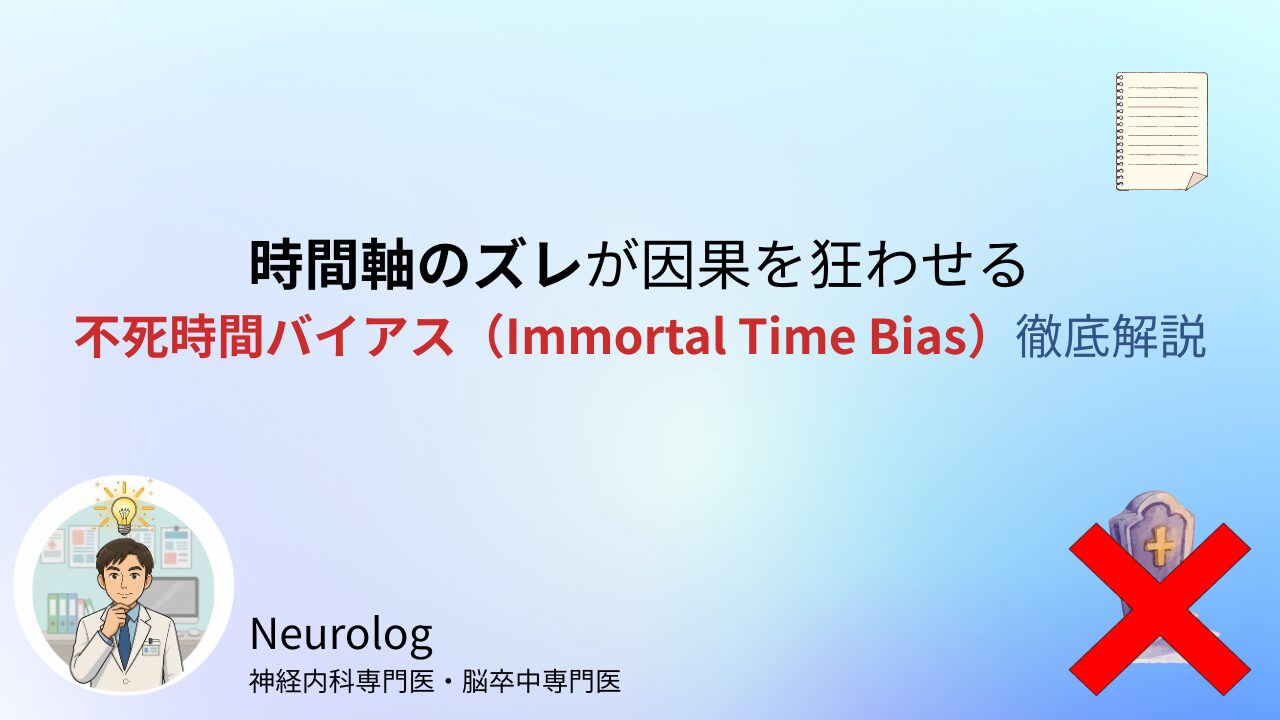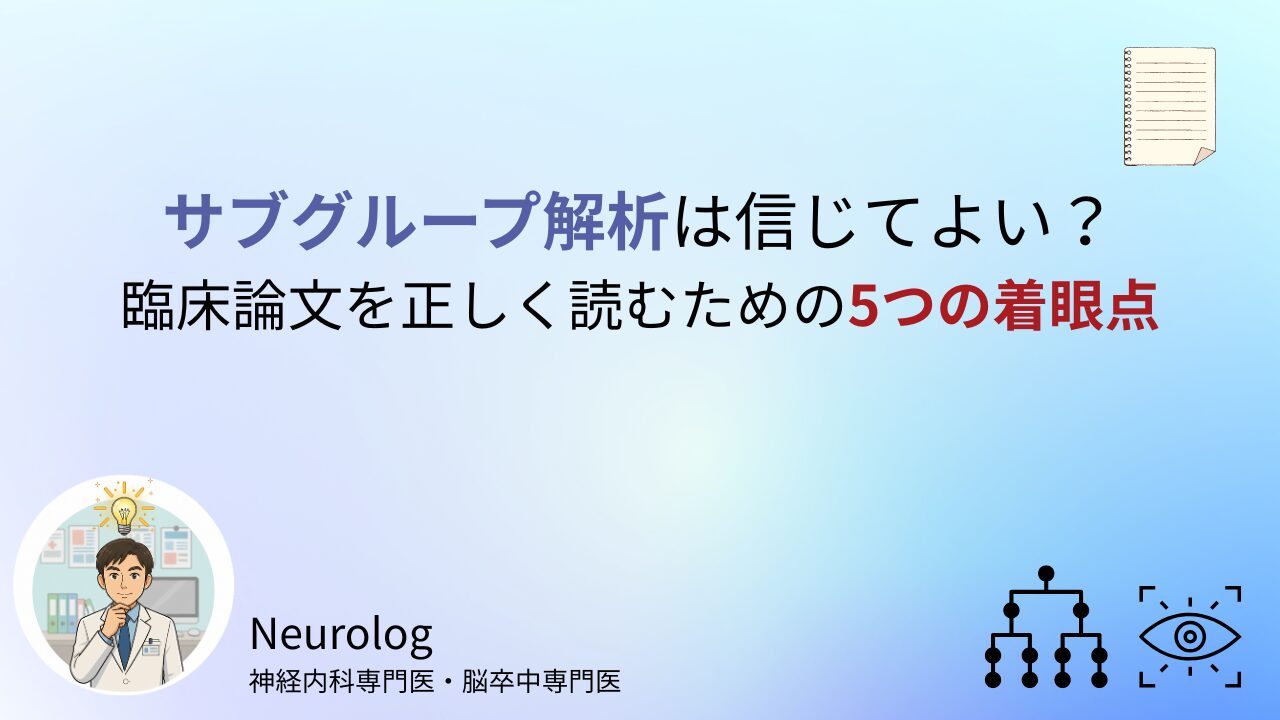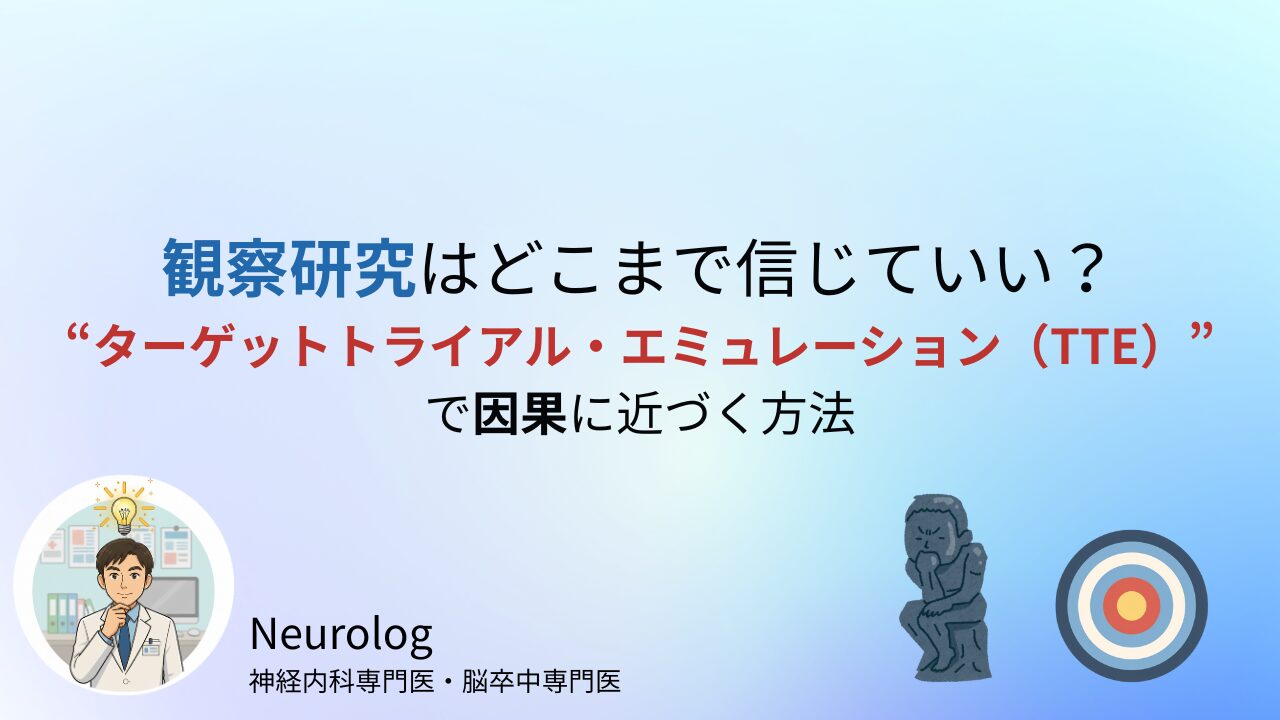その差に“意味”があるか? -p値の限界とNNTの読み方-
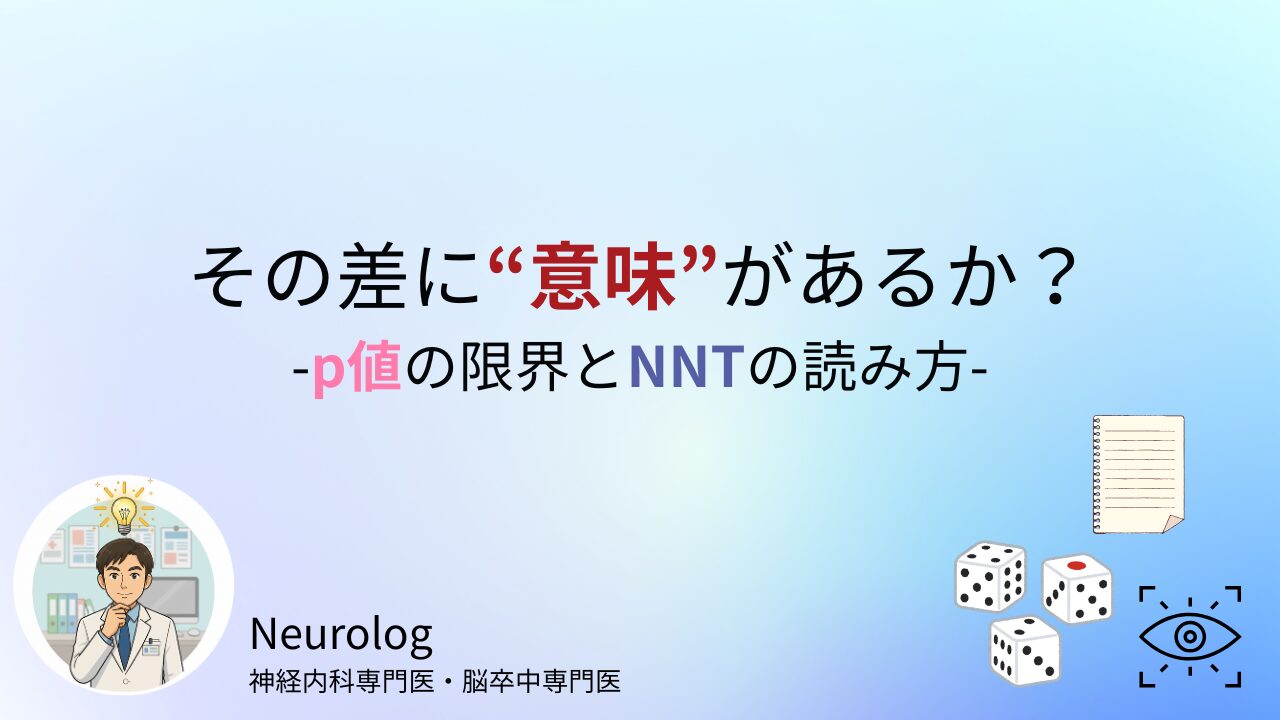
はじめに
論文を読むとき、私たちはつい「p<0.05」という数字に目を奪われがちです。
しかし、その「統計的に有意な差」は、目の前の患者さんにとって本当に「臨床的に意味のある差」なのでしょうか?
この記事のゴールは、論文を単に「有意かどうか」で判断するのではなく、「その治療を何人に行えば、1人に良い結果(あるいは悪い結果)がもたらされるのか?」という、より実践的な視点で読み解く力を身につけることです。
そのための鍵となるのが、治療必要数 (Number Needed to Treat, NNT) と 害必要数 (Number Needed to Harm, NNH) という指標です。
本記事を通じて、p値が持つ限界を理解し、NNT/NNHを使って臨床研究の価値を深く評価する方法を、脳神経内科領域の有名な論文を例に学んでいきましょう。
p値の限界:米国統計協会(ASA)の“6原則”
「有意=重要」ではない/完全開示と推定重視
2016年、米国統計協会 (American Statistical Association, ASA) はp値の誤用を戒める声明を発表しました。
その核心は、「p値は効果の大きさや重要性を示すものではない」「科学的結論をp値の閾値だけで判断すべきではない」という点にあります。
さらに、2019年の特集号 “Statistical Inference in the 21st Century: A World Beyond P < 0.05” では、p値への過度な依存から脱却し、「p=0.049とp=0.051を別世界として扱わない」という姿勢が推奨されました。
私たちが臨床で重視すべきは、「有意か否か」の二元論ではなく、効果の推定値(点推定)とその不確実性の範囲(信頼区間)です。
NNT/NNHの計算式
NNT とは
NNTは「1人の患者で望ましい結果を追加で得るために、何人の治療が必要か」を示す、非常に直感的な指標です。
NNT計算の実際
計算は、まず絶対リスク減少 (Absolute Risk Reduction, ARR) を求めるところから始まります。
- 対照群のイベント発生率(Control Event Rate, CER)
- 介入群のイベント発生率(Experimental Event Rate, EER)
ARR = CER − EER
NNT = 1 / ARR
例えば、
対照群のリスクが15%、
介入群のリスク が10%だった場合、
ARRは 15%-10%=5% (0.05) となり、
NNTは 1 / 0.05 = 20人となります。
有害事象の場合は、絶対リスク増加 (Absolute Risk Increase, ARI) と 危害必要数 (NNH) を用います。
ARI = EER − CER
NNH = 1 / ARI
NNTの落とし穴:期間・ベースライン・アウトカム
NNTを解釈する際は、以下の3点に注意が必要です。
- ベースラインリスク依存: NNTは対照群のリスクに依存します。ハイリスク群ほどNNTは小さくなります。
- 観察期間依存: 90日後と1年後ではイベント率が異なり、NNTも変動します。
- アウトカム定義: 代理マーカーや複合アウトカムに基づくNNTは、臨床的意味を慎重に吟味する必要があります。
実際の臨床試験で体感:
t-PA(NINDS試験)と機械的血栓回収療法(MR CLEAN試験)のNNT
3か月の相対効果と12か月の絶対差(tPA)
1995年に発表されたNINDS試験は、急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(t-PA)の有効性を世界で初めて証明した、まさにランドマークと呼ぶべき臨床試験です。
この試験結果が現代の脳卒中急性期治療の礎を築きました。
- P (Patient): 発症3時間以内の急性期脳梗塞患者
- I (Intervention): アルテプラーゼ(tPA)静注療法
- C (Comparison): プラセボ
- O (Outcome): 機能的転帰
NINDS試験では、3ヶ月時点でtPA群はプラセボ群と比較して「最小〜無障害」となる相対的な確率が少なくとも30%高いことが示されました(相対効果)。
一方で、より長期の12ヶ月時点でも良好な機能転帰の絶対差は11〜13%ポイントで持続しており、これを基にNNTを計算すると、
NNT ≈ 1 / 0.12 ≈ 8.3
となり、NNTは約8〜9人という目安が得られます。
もちろん、症候性頭蓋内出血のリスク(tPA群 6.4% vs プラセボ群 0.6%)も同時に考慮する必要があります。
mRSシフト vs 二値化(MR CLEAN)
2015年に発表されたMR CLEAN試験は、脳主幹動脈閉塞症に対する血管内治療(機械的血栓回収療法)の有効性を証明した、最初のランダム化比較試験です。
この試験を皮切りに肯定的な結果が相次ぎ、脳卒中治療は新たな時代を迎えました。
- P (Patient): 前方循環系の主幹動脈閉塞による急性期脳梗塞患者
- I (Intervention): 血管内治療 + 標準治療
- C (Comparison): 標準治療のみ
- O (Outcome): 90日後のmRS分布
MR CLEAN試験の主要評価項目はmRSのシフト解析であり、血管内治療の有効性を共通オッズ比 1.67 (95%CI 1.21–2.30) で証明しました。
これは「治療によって患者全体のmRSが、より良好な方向へシフトする」ことを意味しますが、直感的に理解しにくい側面もあります。そこで理解の補助として、副次評価項目である機能的自立(mRS 0–2)の割合で二値化して見てみます。
治療群 32.6% vs 対照群 19.1%
ARR = 13.5% (95% CI, 5.9% – 21.2%)
NNT ≈ 1 / 0.135 ≈ 7.4 (95% CI, 約5〜17)
NNTの目安は約7人となります。
ただし、二値化は「mRSが3→2になる」ことと「1→0になる」ことを同じ「成功」として扱ってしまうなど、多くの情報を失います。
必ず一次解析(シフト解析)の結果と併せて解釈することが重要です。
Take Home Message
- p値は統計的な指標であり、臨床的な重要性や効果の大きさを示すものではありません。
- ARRからNNT/NNHを計算することで、治療の臨床的インパクトを直感的に把握できます。
- NNTは便利ですが、ベースラインリスク、観察期間、アウトカムの定義に依存するため、その文脈を理解した上での解釈が不可欠です。
参考文献
- Yaddanapudi LN. The American Statistical Association statement on P-values explained. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2016;32(4):421-423. doi:10.4103/0970-9185.194772
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28096569/ - Di Leo G, Sardanelli F. Statistical significance: p value, 0.05 threshold, and applications to radiomics-reasons for a conservative approach. Eur Radiol Exp. 2020;4(1):18. Published 2020 Mar 11. doi:10.1186/s41747-020-0145-y
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32157489/ - National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 1995;333(24):1581-1587. doi:10.1056/NEJM199512143332401
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7477192/ - Berkhemer OA, Fransen PS, Beumer D, et al. A randomized trial of intraarterial treatment for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2015;372(1):11-20. doi:10.1056/NEJMoa1411587
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25517348/