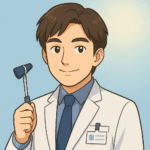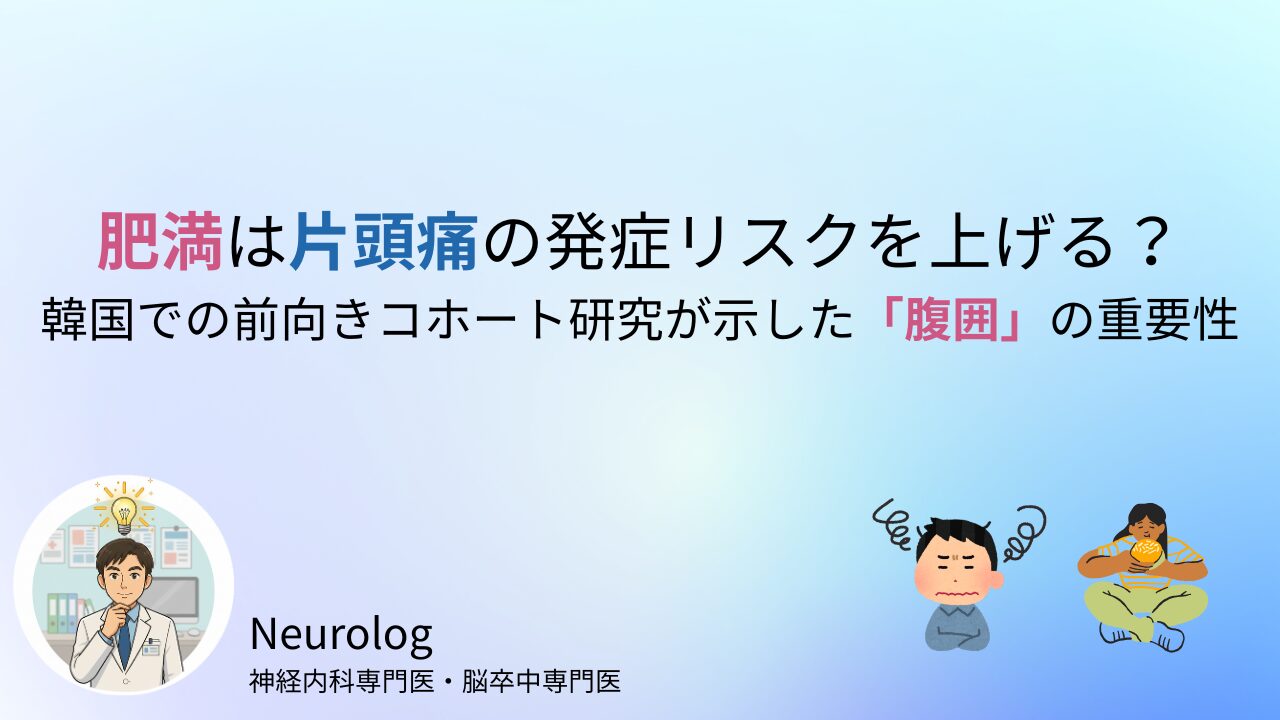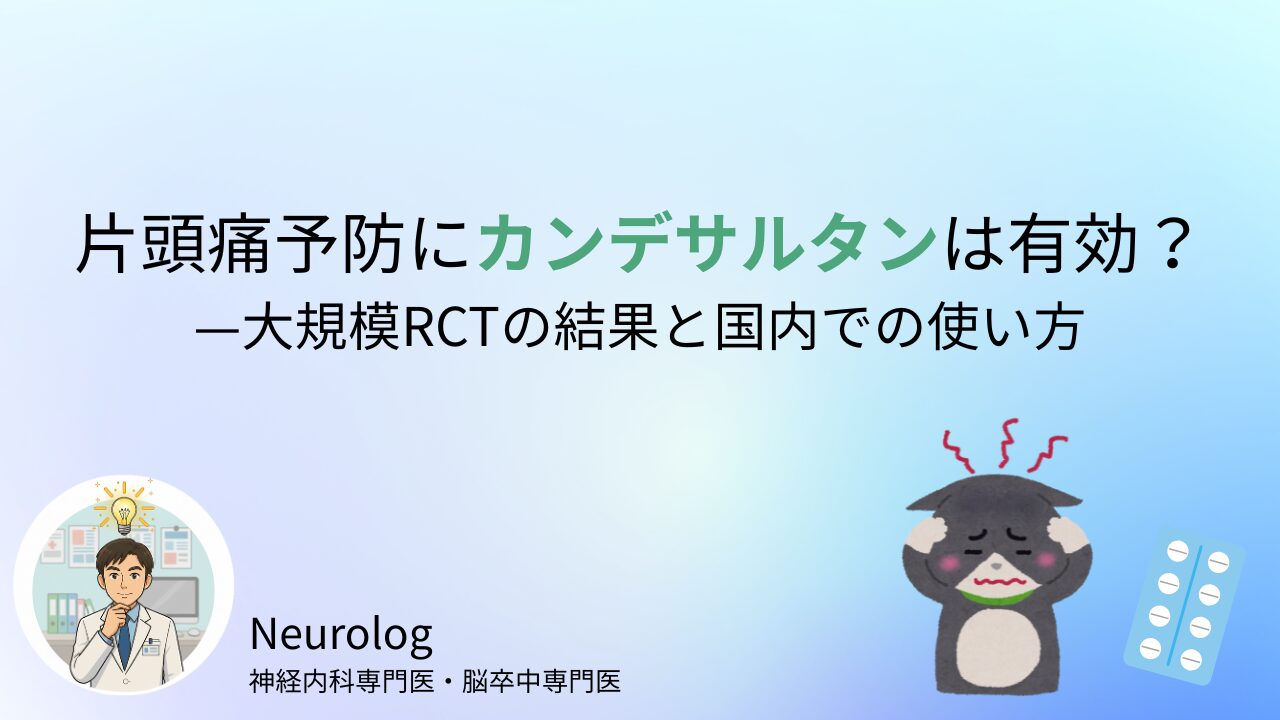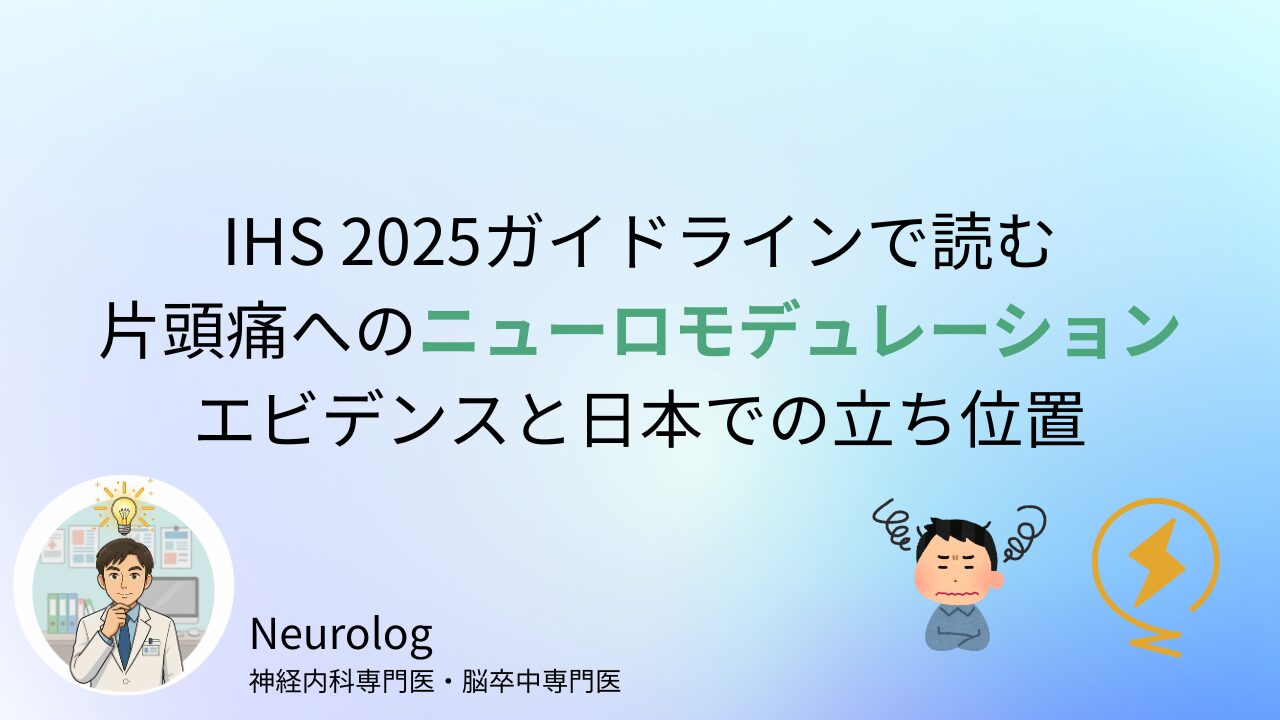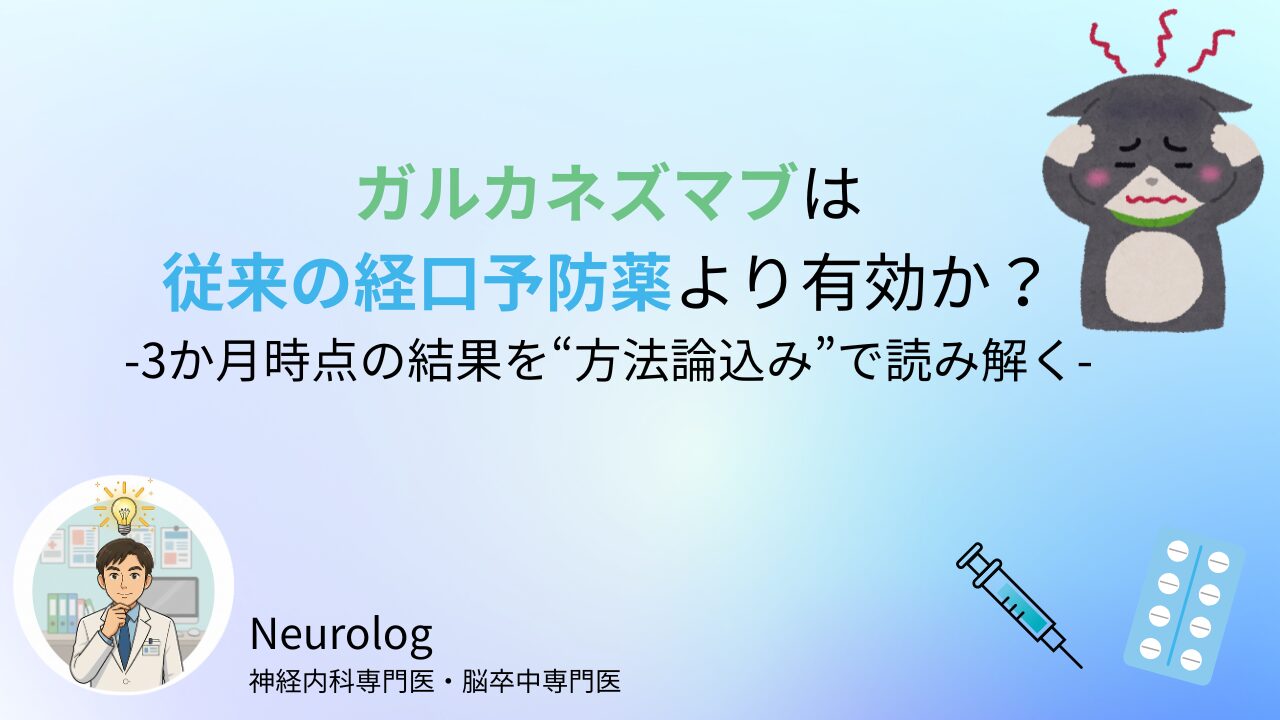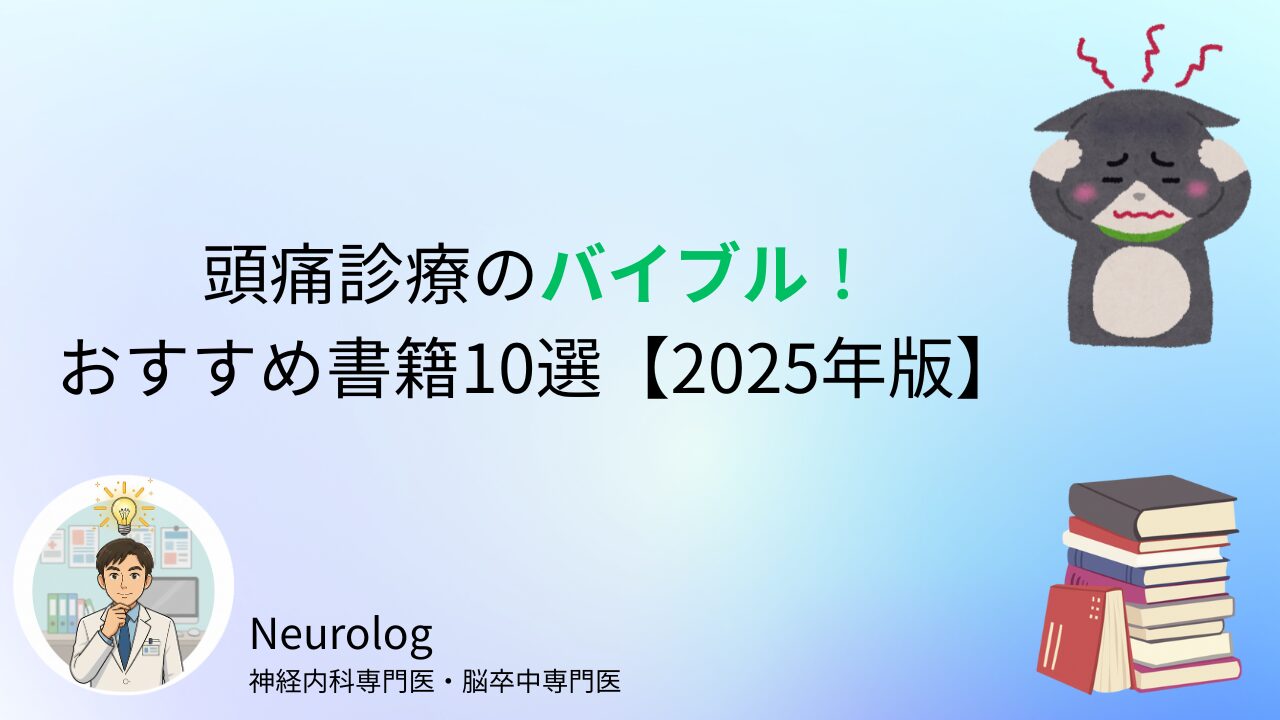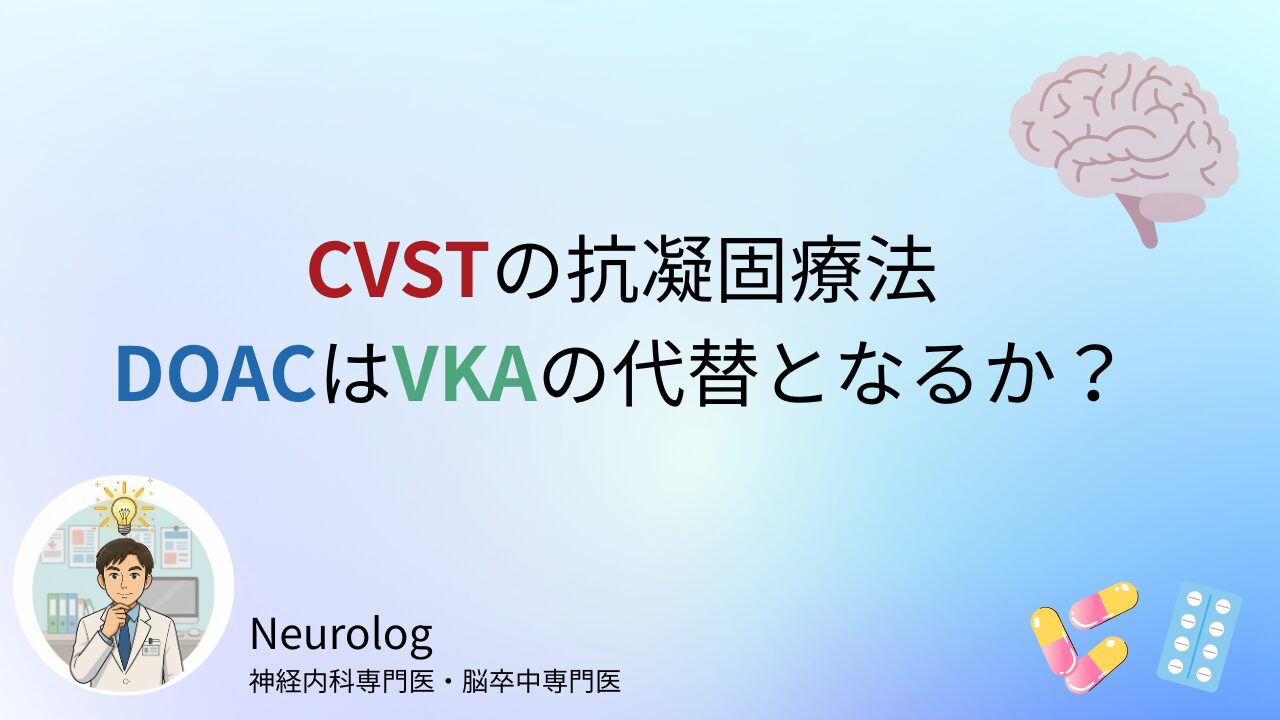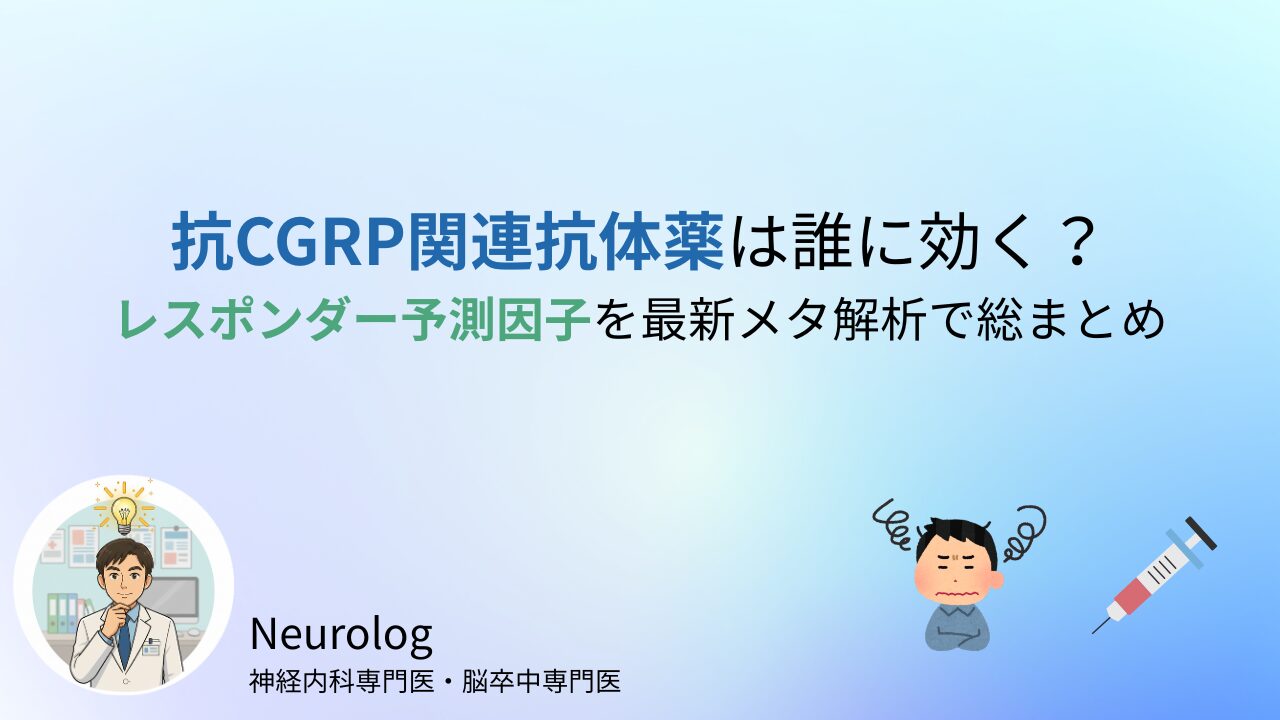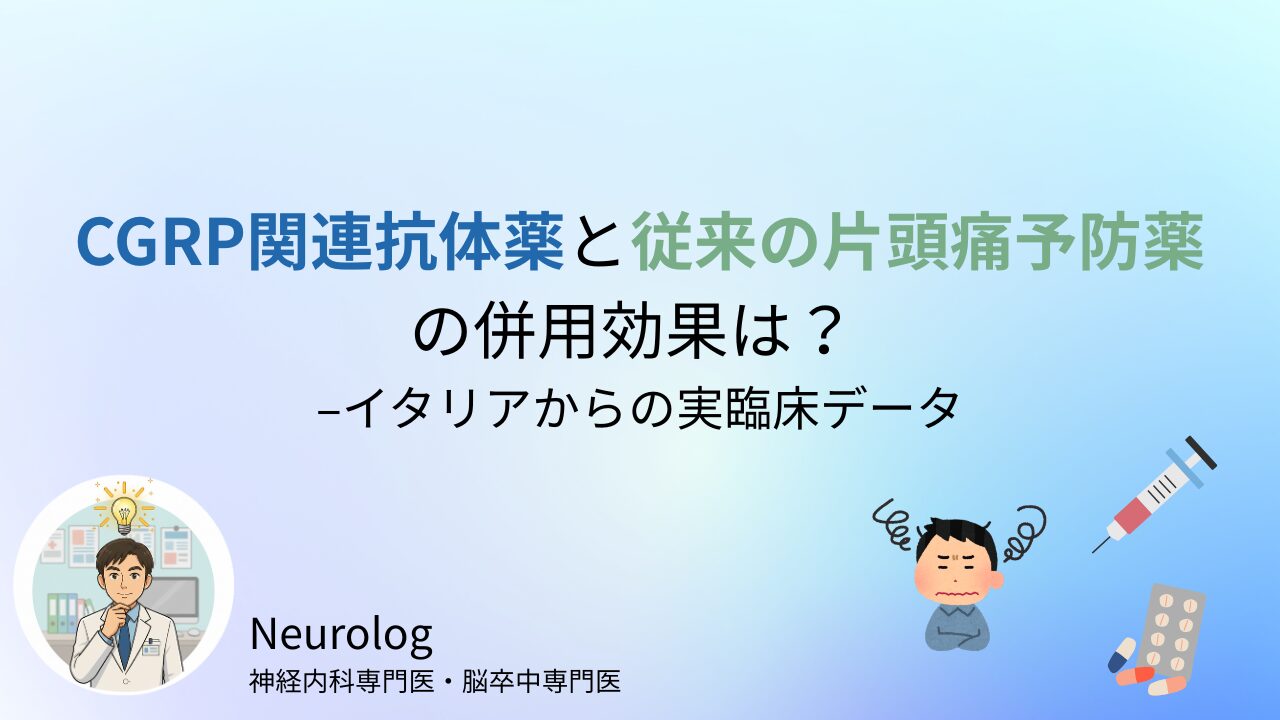片頭痛予防にCGRP抗体薬とゲパントはどっちが効く?—ガルカネズマブ vs リメゲパント直接比較RCTの結論と実臨床での使い分け

片頭痛治療は、CGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide: カルシトニン遺伝子関連ペプチド)関連薬の登場により劇的に変化しました。
現在、片頭痛発作の発症抑制(予防)薬としてCGRPの働きを抑える薬剤には、大きく分けて2種類あります。
- CGRP(受容体)モノクローナル抗体薬(以下、抗体薬; mAb):
- 月1回または3ヶ月に1回の皮下注射薬(例:ガルカネズマブ、エレヌマブ、フレマネズマブ)
- Gepant系薬剤(以下、Gepant):
- 経口薬(例:リメゲパント、アトゲパント)
どちらも従来の予防薬より有効性が高く、副作用も少ないため、海外では第一選択薬として活躍しています。
しかし、ここで新たな疑問が生まれます。「注射(抗体薬)と経口薬(ゲパント)、発症抑制(予防)効果はどちらが優れているのか?」
この最も知りたいClinical Questionに答えるため、最近発表された重要な直接比較試験(Head-to-head RCT)と、その他の間接的な比較研究について、研究デザインの「読み方」も交えながら解説します。
直接対決! ガルカネズマブ vs リメゲパント (CHALLENGE-MIG試験)
これまで、抗体薬とGepantの予防効果を「直接」比較したランダム化比較試験(RCT: Randomized Controlled Trial)は存在しませんでした。
今回ご紹介するのは、その初の直接対決となった CHALLENGE-MIG試験 (NCT05127486) です。
PICO
- P (Patient): 反復性片頭痛(Episodic Migraine: EM)の成人患者 580名
- I (Intervention): ガルカネズマブ(抗体薬) 120mg 皮下注射 月1回(初回ローディング240mg) + プラセボ経口薬 隔日
- C (Control): リメゲパント(ゲパント) 75mg 経口薬 隔日 + プラセボ皮下注射 月1回
- ※リメゲパントは、日本では「ナルティークOD錠 75mg」(ファイザー社)として販売されています。
- O (Outcome): 主要評価項目 – 3ヶ月時点での月間片頭痛日数 (Monthly Headache Days: MHD) がベースラインから50%以上減少した患者の割合(50%レスポンダー率)
- ※本論文ではMHDが用いられましたが、他の多くの片頭痛研究では月間片頭痛日数(MMD: Monthly Migraine Days)が用いられます。
研究デザインと結果
本研究は、第3b/4相、ランダム化、二重盲聞、ダブルダミー試験という、
非常に質の高いデザインで実施されました。
結果はどうだったでしょうか。
主要評価項目(3ヶ月時点の50%レスポンダー率)
- ガルカネズマブ群: 62%
- リメゲパント群: 61%
(差: 1.0% [95% CI: -5.7, 7.7], p=0.70)
驚くべきことに、両群の間に統計学的な有意差はありませんでした。
ガルカネズマブの優越性を示す目的(Superiority trial)でデザインされましたが、
その目的は達成されず、「効果は同等」という結果になりました。
MHDの平均減少日数や安全性プロファイル(副作用)においても、
両群で大きな差は見られませんでした。
Methodの吟味:なぜ「ダブルダミー」が必要か?
この研究の信頼性を高めているのが、
「二重盲検(Double-blind)」と「ダブルダミー(Double-dummy)」という手法です。
- 二重盲検: 患者さんも医師(評価者)も、どちらの治療(実薬かプラセボか)を受けているか分からないようにすることです。
- ダブルダミー: 注射 vs 経口薬のように投与形態が異なる薬剤を比較する際に用いられます。
- ガルカネズマブ群は、「本物の注射」と「偽物の経口薬(プラセボ)」を受け取ります。
- リメゲパント群は、「偽物の注射(プラセボ)」と「本物の経口薬」を受け取ります。
このように、両群とも「注射」と「経口薬」の両方を受ける形にすることで、投与形態の違いによるバイアスを排除し、厳密な盲検化を維持できます。
この厳格なデザインで行われたRCTの結果、「反復性片頭痛の予防において、ガルカネズマブ(月1回注射)とリメゲパント(隔日経口)の効果は、3ヶ月時点では同等である」というのが、現時点で最も信頼性の高い答えとなります。
間接的な比較ではどう? (NMAとMAIC)
直接比較RCTが登場する前は、「間接比較」によって両者の優劣が議論されてきました。
間接比較には主に2つの手法があります。
ネットワーク・メタ解析 (NMA)
ネットワーク・メタ解析(Network Meta-Analysis: NMA)とは、多くの薬剤のRCT(例:A薬 vs プラセボ、B薬 vs プラセボ)の結果を統計学的に統合し、「A薬 vs B薬」のように直接比較試験が存在しない薬剤間の効果も間接的に比較する手法です。
CGRP関連薬に関するNMAも複数報告されています。
Haghdoostらによる2023年のNMAでは、抗体薬とゲパントはいずれも有効かつ忍容性が良好であるとしつつ、一部のアウトカムで抗体薬 (mAb) がゲパントよりもわずかに上振れする傾向が示されました。
一方で、より最近の2025年のNMA報告では、アトゲパント60mg(毎日投与)が、リメゲパント75mg(隔日投与)やガルカネズマブ120mg(月1回投与)よりも一部のアウトカム(MMD減少数など)で優れる可能性が示唆されるなど、結果は一定ではありません。
マッチング調整間接比較 (MAIC) とその限界
マッチング調整間接比較(Matching-Adjusted Indirect Comparison: MAIC)は、
異なる試験の患者データを使い、背景因子(年齢、性別、ベースラインMMDなど)を
統計的に「揃えて」から比較する手法です。
MahonらによるMAICでは、エレヌマブ(抗体薬)とリメゲパント(ゲパント)を比較し、「短期(1~3ヶ月)のMMD減少において、エレヌマブの方が優位であった」と報告されています。
因果推論の視点:なぜ直接比較が重要か?
NMAやMAICは有用ですが、あくまで間接的な比較であり、結果の解釈には細心の注意が必要です。
- MAICの限界: MAICは、異なる試験集団の患者背景を統計的に「揃える(マッチングする)」手法です。このとき、比較可能性を担保するために、特に「効果修飾因子(Effect Modifier)」の分布を揃えることが極めて重要です。もし試験間で効果修飾因子の分布が異なると(例:一方の試験に治療が効きやすい患者群が多い)、治療効果の比較が歪められてしまうからです。
- しかし、どの因子が真の効果修飾因子であるかを事前にすべて特定することは難しく、また「測定されていない(あるいは論文で報告されていない)効果修飾因子」が存在する場合、その影響(一種の残余交絡Residual Confounding)を取り除くことはできず、比較結果には依然としてバイアスが残る可能性があります。
疫学・統計学的な観点からは、エビデンスレベル(=信頼性)は、
直接比較RCT(CHALLENGE-MIG) > NMA > MAIC
となります。
したがって、間接比較でどのような結果が出ていても、
CHALLENGE-MIG試験で「差はなかった」という結果が出た以上、
現時点では「効果は同等レベル」と考えるのが最も妥当です。
日本の最新承認状況と実臨床での使い分け
(2025年11月時点)
臨床現場での薬剤選択において、エビデンスと並んで重要なのが国内の承認状況です。
2025年に大きな動きがありました。
リメゲパント(ナルティーク®OD錠)の承認内容
リメゲパント(国内製品名:ナルティークOD錠 75mg、ファイザー社)は、2025年9月19日に、以下の両適応で製造販売承認を取得しました。
- 片頭痛発作の急性期治療
- 用法:通常、成人にはリメゲパントとして75mgを片頭痛発作時に1回経口投与する。
- 片頭痛発作の発症抑制(予防)
- 用法:通常、成人にはリメゲパントとして75mgを1日1回、隔日経口投与する。
これにより、CHALLENGE-MIG試験で有効性が示された「リメゲパント隔日投与」が、
日本国内でも保険診療で実践可能となります。
アトゲパント(アクヒタ®)の状況
もう一つの経口予防ゲパントであるアトゲパントは、2025年3月14日に国内承認申請が行われましたが、現時点(2025年10月現在)では未承認です。
したがって、現在、日本で使用できる経口Gepantは、リメゲパント(ナルティーク®OD錠)のみとなります。
実臨床での使い分けのヒント
CHALLENGE-MIG試験の結果(効果は同等)と、ナルティーク®の承認を踏まえると、
実臨床での選択基準は明確です。
- 投与形態とアドヒアランス最大の選択基準は、患者さんのライフスタイルと好みです。
- 抗体薬(注射): 月1回(または3ヶ月に1回)の投与で済むため、毎日の服薬が困難な方、飲み忘れが多い方に適しています。
- ゲパント(経口薬:ナルティーク®): 隔日の服薬が可能で、注射を好まない方に適しています。アドヒアランスの維持が鍵となります。
- 急性期治療薬との兼ね合い:ナルティークは「急性期治療」と「発症抑制(予防)」の両方で承認されたユニークな薬剤です。1日1錠までの投与のため、予防目的で内服済みの日に頭痛が生じた場合は、NSAIDsやトリプタンなどの他の急性期治療薬で対処することになります。
Take Home Message
- ガルカネズマブ(抗体薬) vs リメゲパント(Gepant)の予防効果を直接比較した初のRCT (CHALLENGE-MIG試験) では、3ヶ月時点での50%レスポンダー率に有意差はなかった(62% vs 61%, p=0.70)。
- (日本の状況)リメゲパント(ナルティーク®OD錠)は2025年9月19日、「急性期治療」と「発症抑制(予防)」の両適応で承認された。予防用法は75mg隔日投与である。
- (日本の状況)アトゲパントは2025年3月に承認申請中であり、現時点(2025年10月)では未承認である。
- NMAやMAIC(間接比較)では薬剤間で差が示唆される報告もあるが、交絡の限界があり、信頼性の高い直接比較RCTの結果(=同等)を優先して解釈すべきである。
- 実臨床では、効果の差よりも「注射(月1回)」と「経口薬(隔日)」という投与形態の違いが選択の鍵となる。患者さんの好み、ライフスタイル、アドヒアランスの見込みを最優先に決定すべきである。
よくある質問 (FAQ)
Q1: 日本でリメゲパント(ナルティーク)は片頭痛予防に使えますか?
A1: はい。2025年9月19日に「片頭痛発作の急性期治療」および「片頭痛発作の発症抑制(予防)」の両適応で承認されました。発症抑制(予防)の用法は「75mgを1日1回、隔日経口投与」です。
Q2: 注射(抗体薬)と経口薬(ゲパント)、直接比較ではどちらが優れていますか?
A2: 最新の直接比較RCT(CHALLENGE-MIG試験)では、ガルカネズマブ(注射)とリメゲパント(経口・隔日)の3ヶ月時点での発症抑制効果は同等でした(50%レスポンダー率: 62% vs 61%, p=0.70)。
Q3: アトゲパントの国内の状況はどうなっていますか?
A: 2025年3月14日に製造販売承認申請が提出されており、現時点(2025年10月22日)では審査中であり、まだ承認されていません。
参考文献
- Schwedt TJ, Myers Oakes TM, Martinez JM, et al. Comparing the Efficacy and Safety of Galcanezumab Versus Rimegepant for Prevention of Episodic Migraine: Results from a Randomized, Controlled Clinical Trial. Neurol Ther. 2024;13(1):85-105. doi:10.1007/s40120-023-00562-w
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37948006/ - Haghdoost F, Puledda F, Garcia-Azorin D, Huessler EM, Messina R, Pozo-Rosich P. Evaluating the efficacy of CGRP mAbs and gepants for the preventive treatment of migraine: A systematic review and network meta-analysis of phase 3 randomised controlled trials. Cephalalgia. 2023;43(4):3331024231159366. doi:10.1177/03331024231159366
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36855951/ - Mahon R, Tiwari S, Koch M, et al. Comparative effectiveness of erenumab versus rimegepant for migraine prevention using matching-adjusted indirect comparison. J Comp Eff Res. 2024;13(3):e230122. doi:10.57264/cer-2023-0122
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38174577/