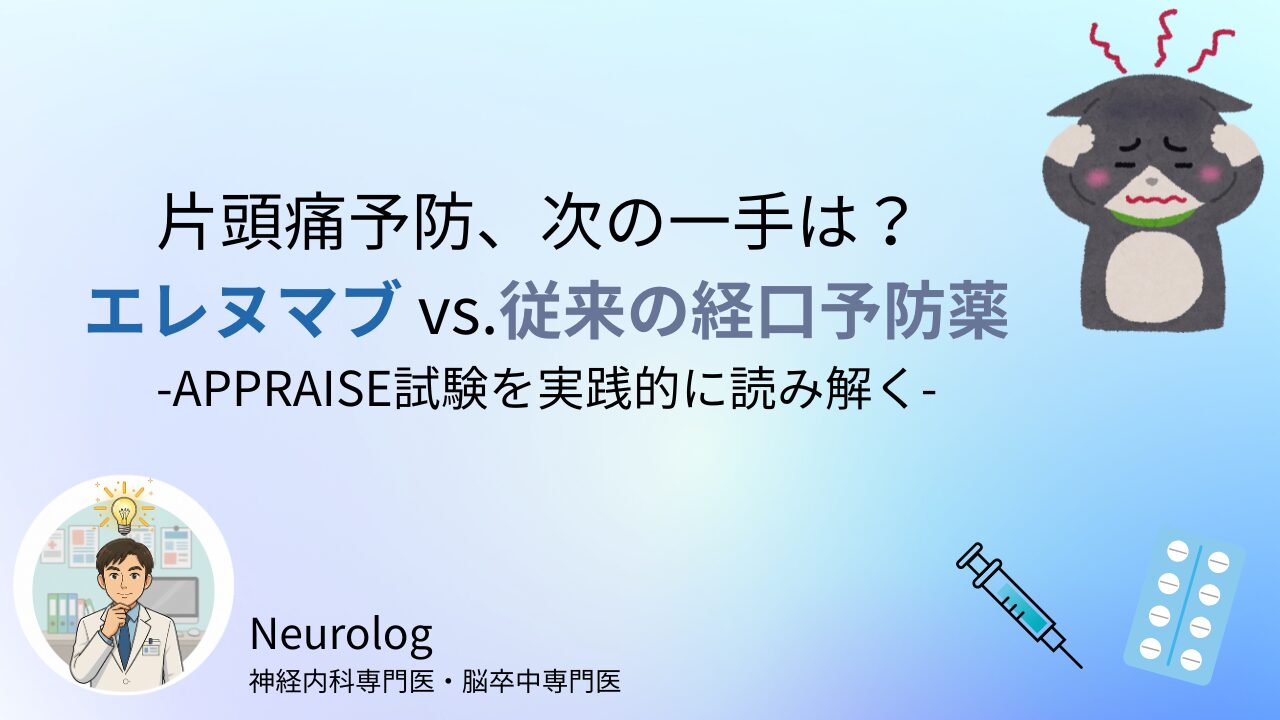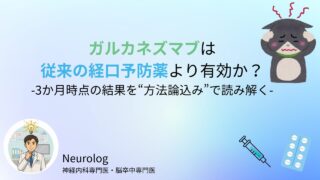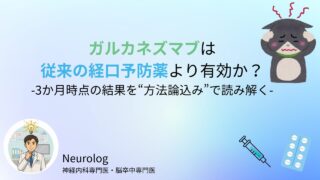はじめに
反復性片頭痛の予防療法で「いつから抗CGRP関連薬を考慮すべきか」を検討するうえで重要なAPPRAISE試験(JAMA Neurol 2024)を、研究デザインと因果推論の観点も交えて要点整理します。
実臨床でのmAbと経口薬の比較は、前向き観察コホートTRIUMPH試験の3か月結果(Headache 2025)が詳しいので、あわせてどうぞ。
PICO(誰に・何を・何と比べ・何をみたか)
- P(患者):成人の反復性片頭痛(月間片頭痛日数 4–14日)、過去1–2種類の予防薬で効果が不十分。
- I(介入):エレヌマブ早期投与(抗CGRP受容体抗体)。
- C(比較):医師選択の非特異的経口予防薬(OMPMs:β遮断薬、トピラマート、三環系 抗うつ薬ほか)。
- O(アウトカム):12か月時点で当初割り付けられた治療を継続し、かつ月間片頭痛日数が50%以上減少した患者の割合(複合主要評価項目)。
研究デザインの要点と解釈
- 国際多施設・オープンラベルRCT(第4相試験):実臨床に近い意思決定(途中での薬剤変更も可)を許容しつつ、「継続率 × 有効性」を主要評価項目に据えた点が非常に実践的です。
- オープンラベルの限界:プラセボ効果や新薬への期待バイアスの懸念はありますが、主要評価を12か月という長期に設定しているため、短期的なプラセボ効果の影響は相対的に小さい設計と考えられます。
主な結果
- 複合主要評価項目達成率:
- エレヌマブ群: 56.2%
- 従来経口薬群: 16.8%
- オッズ比 6.48(95%CI 4.28–9.82, P<0.001)
- 患者さんの主観的な改善度(PGIC):
- エレヌマブ群: 76.0%
- 従来経口薬群: 18.8%
- オッズ比 13.75(95%CI 9.08–20.83, P<0.001)
- 忍容性・継続性:
- 治療変更に至った割合:エレヌマブ群 2.2% vs 従来経口薬群 34.6%
- 有害事象による中止:エレヌマブ群 2.9% vs 従来経口薬群 23.3%
いずれもエレヌマブが圧倒的な優越性
- 比較された従来経口薬の内訳:β遮断薬 31.3%、トピラマート 22.1%、三環系抗うつ薬 15.9% などでした。※ トピラマートは本邦では保険適用外
批判的吟味(Strengths/Limitations)
- Strengths: 12か月という長期の効果を検証した点、実臨床を反映した「継続率×効果」という複合評価項目、現実的な薬剤変更を許容したデザイン。
- Limitations: オープンラベルであることによる期待・観察バイアスの可能性、比較された従来経口薬の選択が地域で異なる点、対象が慢性片頭痛よりは反復性片頭痛が主体であった点。
実臨床への落とし込み(実装ガイド)
- 対象患者のイメージ: 月の片頭痛日数が4日以上あり、既に1〜2剤の経口予防薬を試したけれど効果が不十分、という患者さんには、次の一手として抗CGRP関連薬を早期に提案することを積極的に検討すべきでしょう。
- 外的妥当性の注意点: この研究で比較された従来経口薬は欧米で主流のものが多く、日本で頻用されるロメリジンやバルプロ酸の比率は高くありません。この点は念頭に置きつつ、個々の患者さんの背景を考慮して結果を適用する必要があります。
- ガイドライン動向と日本の現状: 米国頭痛学会(AHS)は2024年の声明で「CGRP関連薬を一次選択肢として推奨する」と発表していますが、日本では適正使用指針上、既存治療1剤以上で効果不十分な場合や忍容性が悪い場合に用いる薬剤と位置づけられており、第一選択薬にはできません。海外の最新動向を参考にしつつも、国内のルールに準拠した処方が求められます。
RCTの外側=“実臨床”での比較は下記の記事に要点をまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. まずは経口薬を何剤か試してから抗CGRP関連薬に進むべき?
A1. 米国頭痛学会の2024年声明は「一次選択肢として許容する」としていますが、これは米国の見解です。日本では適正使用指針により、既存の経口予防薬などを試した上で効果が不十分な場合に抗CGRP関連薬の適応となります。まずは国内のガイドラインに沿った治療選択が基本です。
Q2. コストや保険適用は?
A2. 薬剤費そのものは高額ですが、近年は治療中断によって生じるコスト(救急受診、生産性の低下、急性期治療薬の増量など)や片頭痛による経済的損失まで含めた総費用で議論される傾向にあります。
Q3. 比較された従来経口薬(OMPM)の「どれ」が多かった?
A3. 初期に割り付けられた薬剤の内訳は、β遮断薬が31.3%、トピラマートが22.1%、三環系抗うつ薬が15.9%などで、日本の日常診療で使われる薬剤の割合とは少し異なる点に注意が必要です。
Take-Home Message
✅ 「継続率 × 効果」を同時に評価する実用的な指標で、エレヌマブが従来経口薬に明確に優越することを示した。
✅ 副作用が原因の治療中止・変更も極めて少なく、“続けやすく、かつ効果も高い”という点が数字で示された。
参考文献(主要ソース)
- Pozo-Rosich P, Dolezil D, Paemeleire K, et al. Early Use of Erenumab vs Nonspecific Oral Migraine Preventives: The APPRAISE Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2024;81(5):461-470. doi:10.1001/jamaneurol.2024.0368
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38526461/
- Charles AC, Digre KB, Goadsby PJ, Robbins MS, Hershey A; American Headache Society. Calcitonin gene-related peptide-targeting therapies are a first-line option for the prevention of migraine: An American Headache Society position statement update. Headache. 2024;64(4):333-341. doi:10.1111/head.14692
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38466028/
関連
※本ブログは、私個人の責任で執筆されており、所属する組織の見解を代表するものではありません。
About me
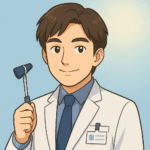
急性期市中病院で勤務する脳神経内科医です。
得意分野は脳卒中・頭痛です。神経内科専門医・脳卒中専門医で、頭痛専門医を目指して研鑽中です。mJOHNSNOW Fellow(2期)。
医学論文をわかりやすく解説し、明日から使える実践知を発信します。個別の医療相談にはお答えできかねます。本サイトの投稿は個人的見解です。