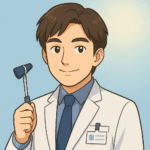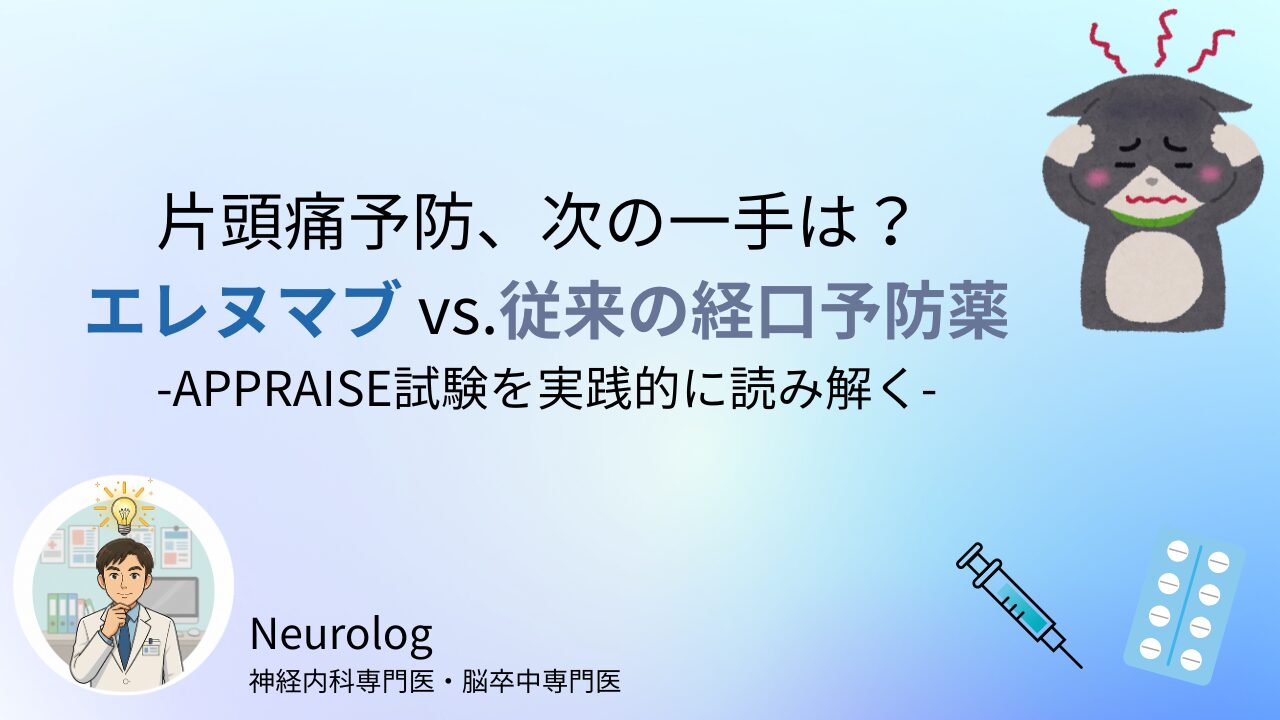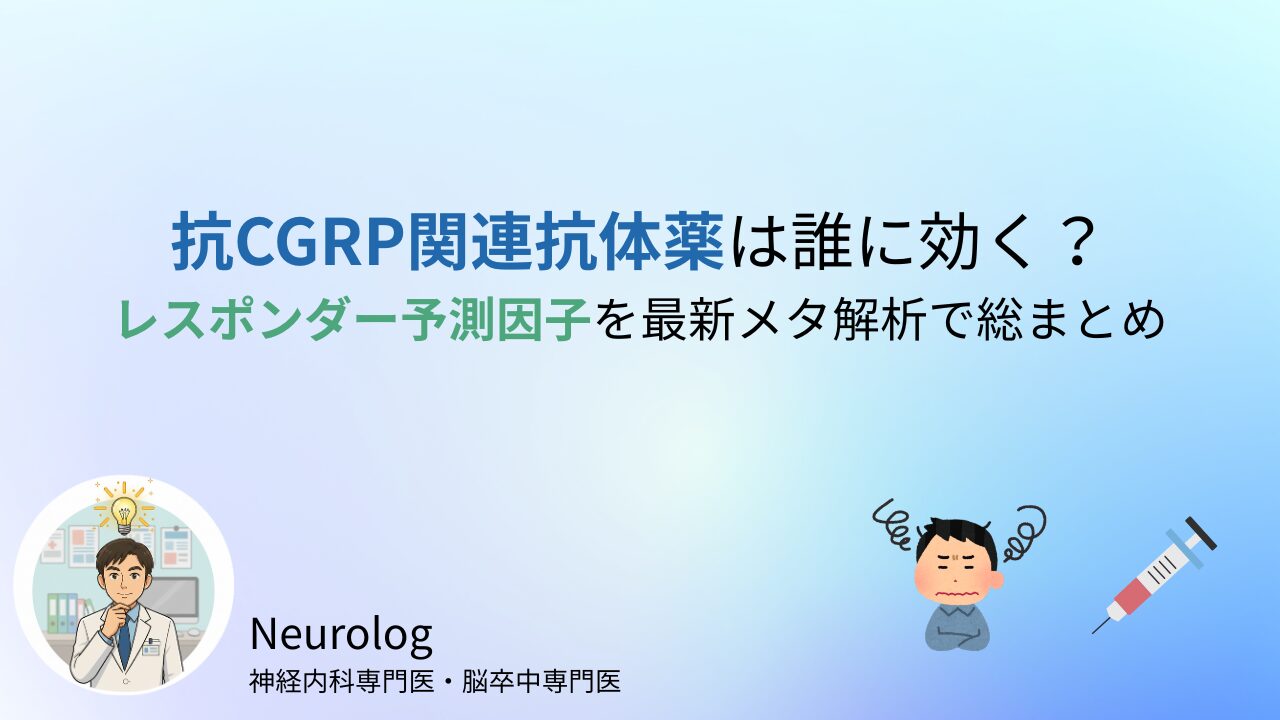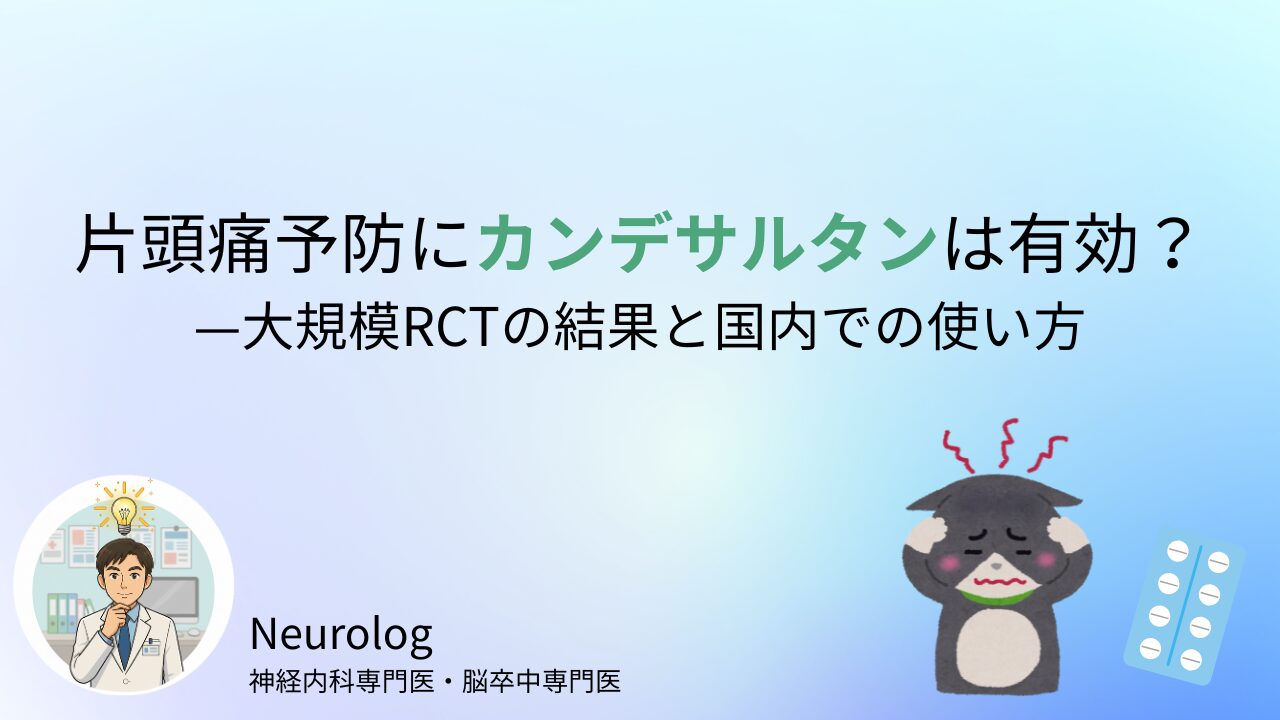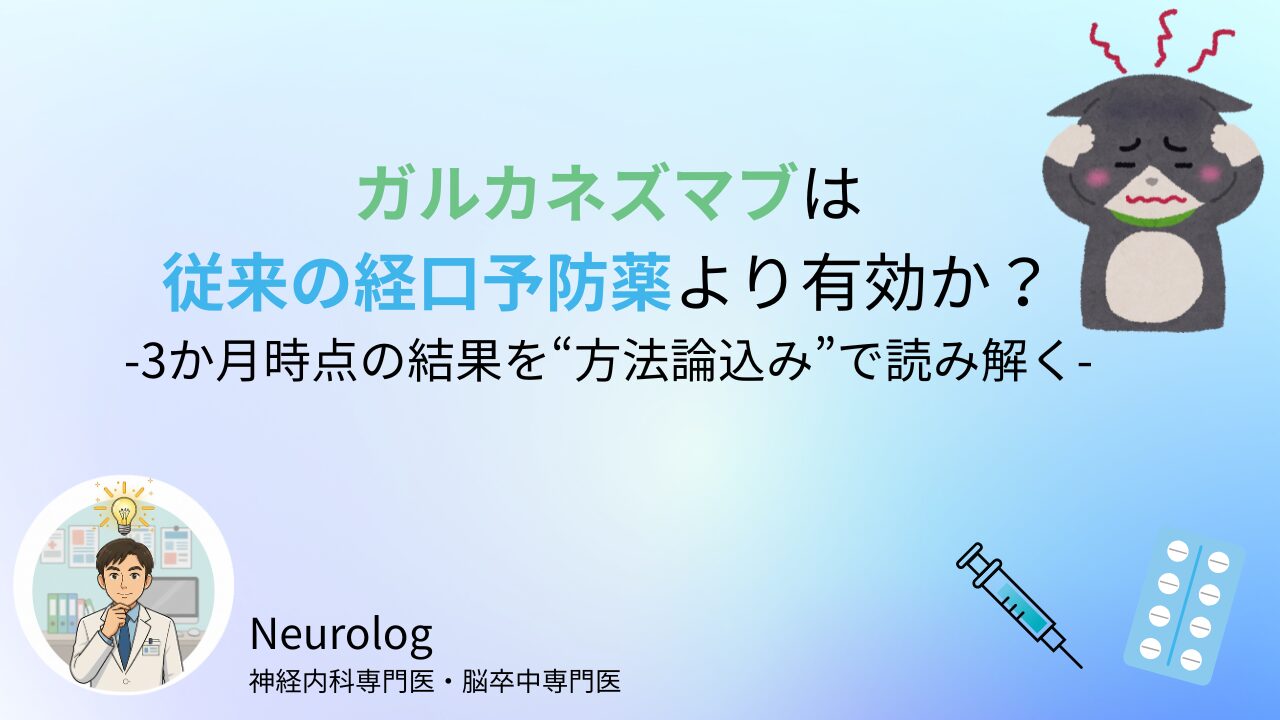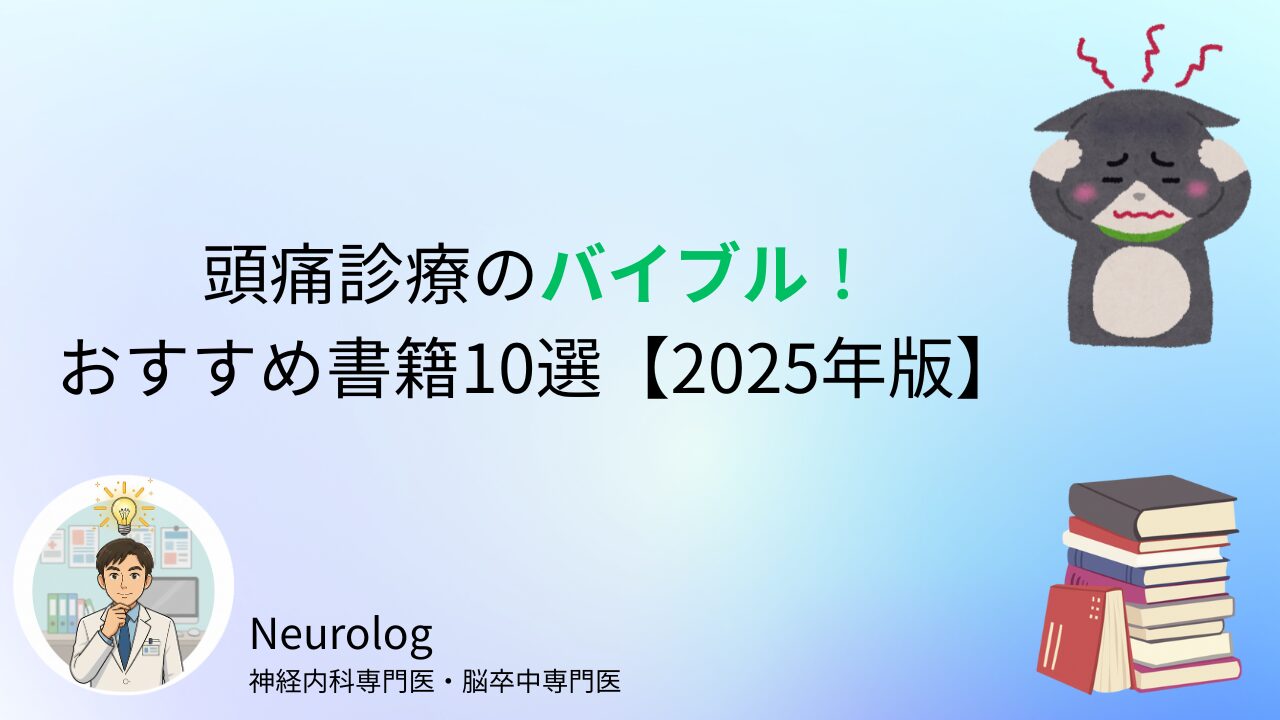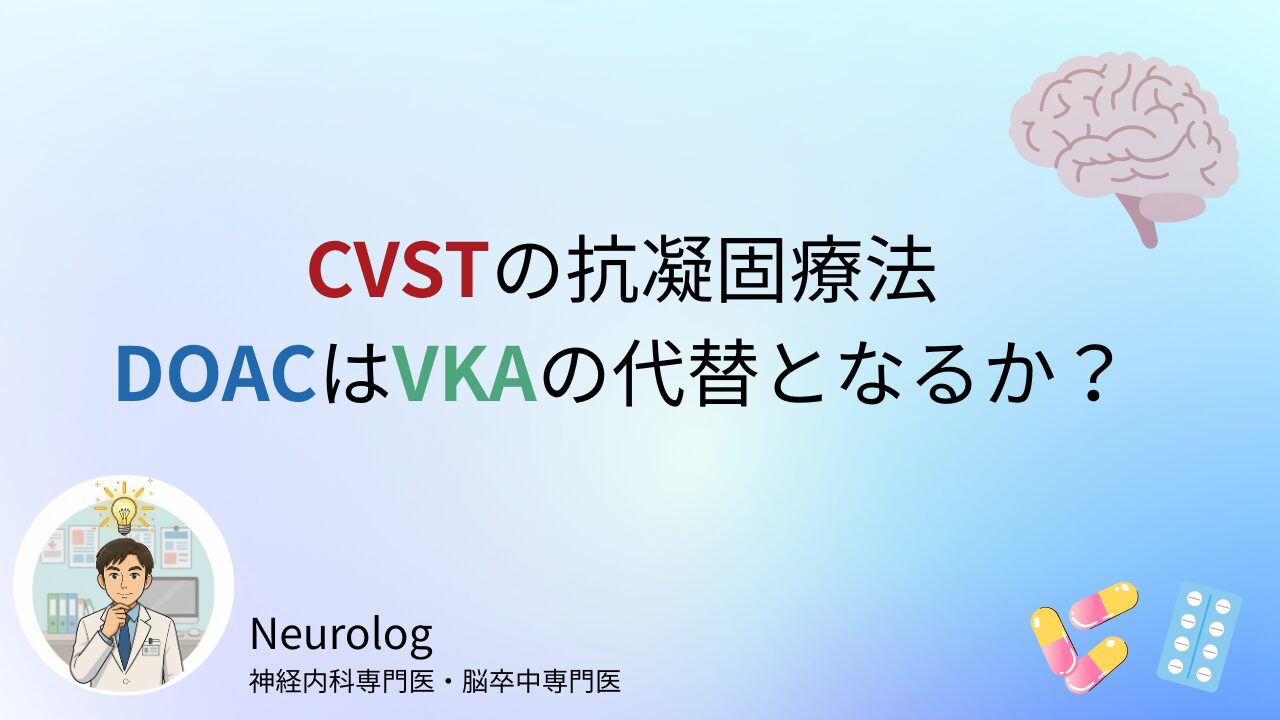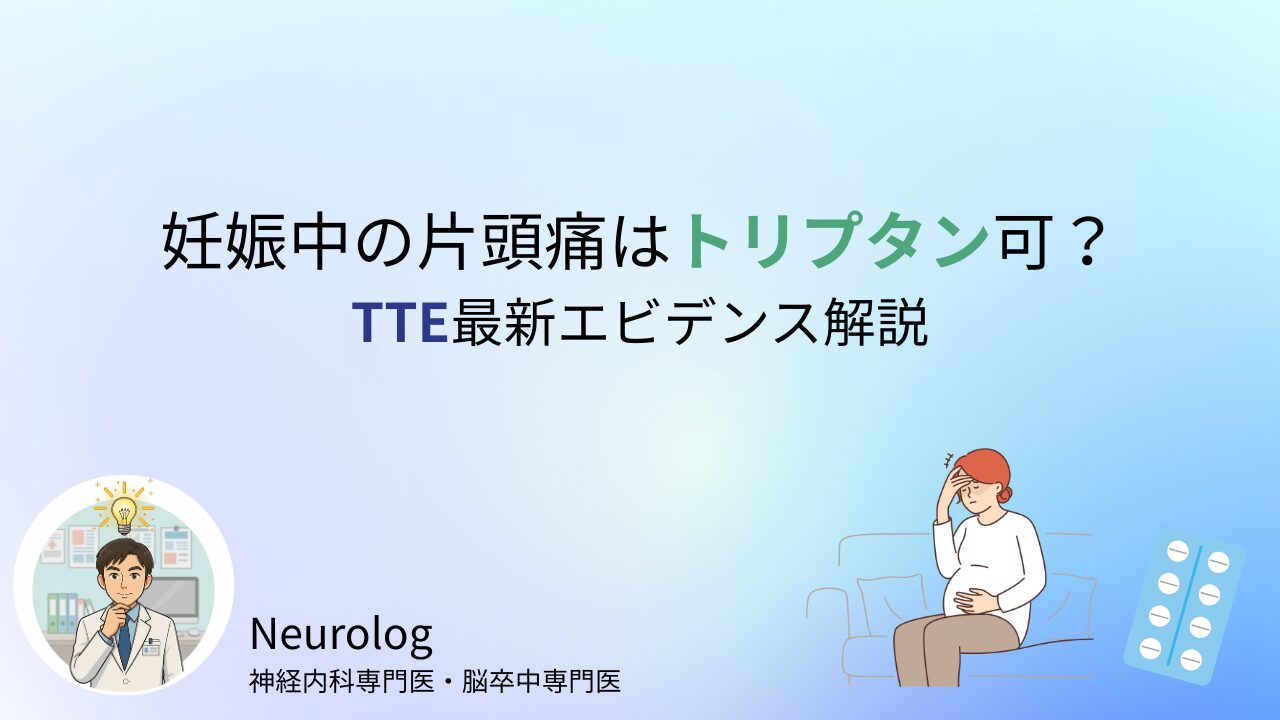CGRP関連抗体薬と従来の片頭痛予防薬、併用効果は? –イタリアからの実臨床データ
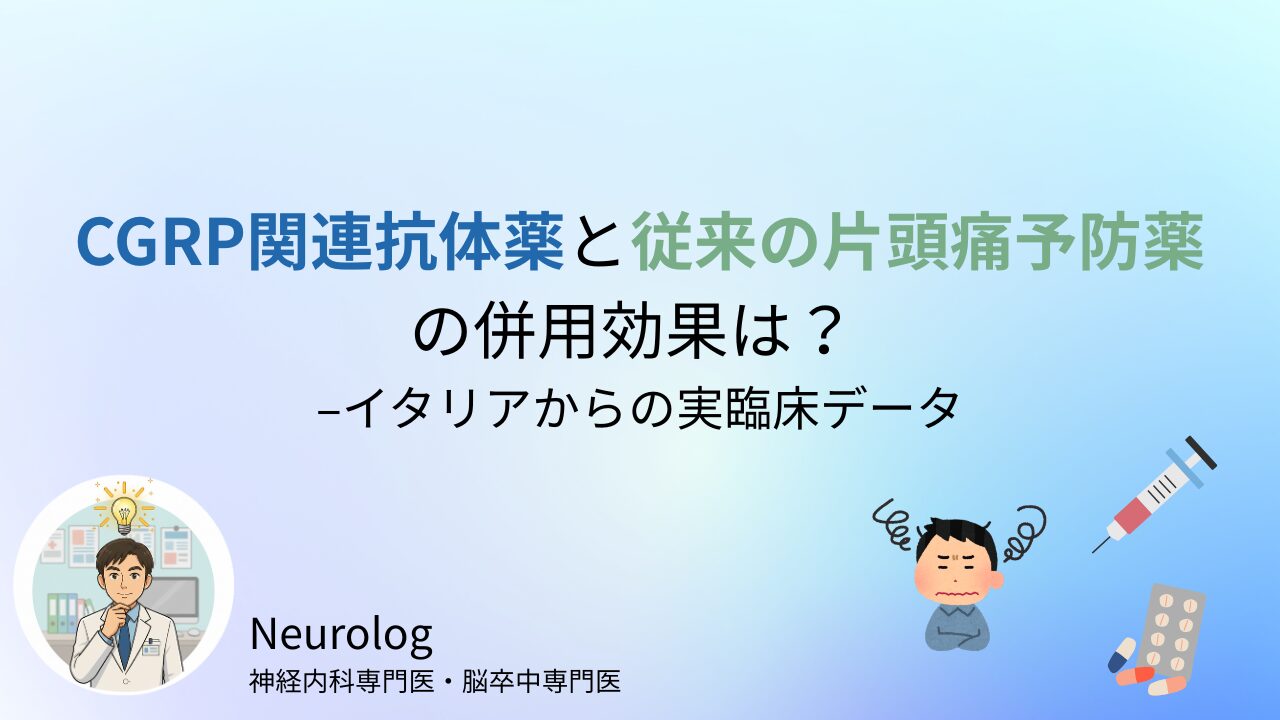
はじめに
片頭痛治療はCGRP関連モノクローナル抗体(CGRP-mAbs: Calcitonin Gene-Related Peptide monoclonal antibodies)の登場により劇的に変化しました。高い有効性と忍容性から、多くの患者さんが恩恵を受けています。
一方で、実臨床では「すでに従来の予防薬(バルプロ酸、トピラマート、アミトリプチリン、プロプラノロールなど)を内服中の患者さんにCGRP-mAbsを導入する」ケースが少なくありません。
このとき、先生方はどうされていますか?
「CGRP-mAbsを始めるのだから、今までの薬はすぐに中止すべき?」
「それとも、効果が安定するまで併用を続けるべき?」
この臨床現場での疑問(Clinical Question)に対して、一つの答えを与えてくれるリアルワールドデータが、イタリアから報告されました。
論文のPICO
2025年10月『Cephalalgia』掲載の多施設前向き観察研究です。
- P (Patient):CGRP-mAbsを初めて開始した片頭痛患者。(登録599名、解析対象555名(イタリア多施設コホート))
- I (Intervention):CGRP-mAbs開始時に標準的な片頭痛予防薬(SPTs: Standard Preventive Treatments)を併用していた群(SPT+群:195名)
- C (Comparison):CGRP-mAbsを単剤で使用した群(SPT−群:360名)
- O (Outcome):6か月時点(T6)の月間片頭痛日数(MMD: Monthly Migraine Days)変化(主要アウトカム)、および50%レスポンダー率・MIDAS・NRS変化など(副次アウトカム)
※ 使用されたCGRP-mAbsの内訳は、ガルカネズマブ 260名 (46.8%)、エレヌマブ 167名 (30.0%)、フレマネズマブ 128名 (23.1%) でした。ただし、エレヌマブは本邦承認用量と異なる。
研究概要と主な結果
本研究は、イタリアの頭痛センターによる多施設前向き観察研究(prospective observational multicentric study)で、CGRP-mAbsを導入した患者を12か月間追跡しています。解析対象は、1年の治療サイクルを完遂した555名です。
ベースラインの違い
治療開始時(T0)の月間片頭痛日数(MMD)は、SPT併用群(SPT+)の方が有意に少ない結果でした:
18.6 ± 7.8 vs 20.3 ± 7.2, p = 0.007
MMDの変化
6か月時点(T6)までのMMD減少幅は、SPT併用群(SPT+)で −10.4 ± 7.2、単剤群(SPT−)で −12.4 ± 7.4 でした(p = 0.007)。
6か月時点の効果
T6時点でのMMD自体は両群でほぼ同等(p = 0.984)でした。
また、50%レスポンダー率も差はなく(OR 0.779, 95% CI 0.534–1.138, p = 0.205)、MIDASスコアおよびNRS(Numeric Rating Scale:痛みの強さ)の改善度も両群で有意差はありませんでした(それぞれ p = 0.919, p = 0.664)。
併用薬(SPTs)の変化
SPTsを併用している患者の割合は、T0(35.0%)→ T6(28.8%)→ T12(19.6%)へと段階的に減少しました。
研究デザインの吟味:内的妥当性と外的妥当性
この研究は「前向き観察研究」であり、このデザインの強みと弱みを「内的妥当性」と「外的妥当性」の観点から評価することが不可欠です。
外的妥当性 (External Validity) : 高い
本研究の最大の強みは、外的妥当性(一般化可能性)が高い点にあります。
- リアルワールドデータ (RWD): RCT(ランダム化比較試験)のように厳格な除外基準がなく、日常診療で実際に遭遇する「従来の予防薬を併用中」「併存疾患がある」といった多様な患者が含まれています。
- 多施設共同研究 (Multicentric study): イタリア国内の複数の頭痛センターからのデータであり、単一施設の特殊な治療方針に偏っていない点も、一般化可能性を高めています。
このため、研究結果は日本の実臨床現場に当てはめて考える上でも、非常に参考になると言えます。
内的妥当性 (Internal Validity) : 低い〜中程度
一方で、内的妥当性(=研究結果の真実性、因果関係の証明力)には複数の限界が存在します。
- ランダム化の欠如: 本研究はRCTではないため、患者を「併用群(SPT+)」と「単剤群(SPT-)」にランダムに割り付けていません。治療選択は臨床医の判断に委ねられています。
- 交絡(Confounding): これが内的妥当性を脅かす最大の要因です。
- 適応バイアス (Indication Bias): ベースラインのMMDが単剤群(SPT-)の方が有意に重症(20.3 vs 18.6日)でした。これは、単剤群(SPT-)に「従来薬が全く効かなかった/副作用で中止せざるを得なかった」ような、より治療抵抗性の患者が集まっている可能性を強く示唆します。この背景の違いが、見かけ上の結果(例:MMDの減少幅)に影響を与えている可能性があります。
- 交絡調整の限界: 著者らは多変量解析を用いていますが、これは主に「SPT継続の予測因子」を探るためであり、主要アウトカム(6ヶ月後のMMD改善度)に対する交絡調整は限定的です。
- 残余交絡 (Residual Confounding): 上記の治療抵抗性や、測定されていない因子(例:患者のアドヒアランス、心理社会的背景)が統計的に調整されないまま結果に影響している可能性(=残余交絡)が残ります。
これらの要因により、「SPT併用の有無が、CGRP-mAbsの効果に(因果的に)影響しなかった」と断定することは困難です。観察研究であり、内的妥当性には限界があります。
臨床的解釈(妥当性を踏まえて)
この研究は、「内的妥当性は低いが、外的妥当性は高い」というRWDの典型的な特徴を示しています。
この点を踏まえると、本研究のメッセージは次のように整理されます。
- 外的妥当性の観点: 実臨床(リアルワールド)において、CGRP-mAbsを従来の予防薬(SPTs)と併用しながら開始している患者群は、単剤で開始した患者群と比べて、6ヶ月後の臨床アウトカムに(少なくとも見かけ上は)大きな差はなかった。
- 内的妥当性の観点: ただし、これは「併用しても効果は変わらない」という因果関係を証明するものではない。背景にある交絡(特に治療抵抗性)が結果に影響している可能性を排除できない。
Take Home Message ✍️
- 本研究は、実臨床への一般化可能性(外的妥当性)が高いリアルワールドデータ(RWD)です。
- 一方で、観察研究であるため交絡バイアス(特に適応バイアス)の影響を受けており、内的妥当性(因果関係の証明力)は限定的です。
- これらの限界を認識した上で、結果を解釈するならば、「CGRP-mAbs開始時に既存の予防薬を継続しても、単剤群と比較して臨床効果が大きく損なわれることはない」という実臨床の感覚を支持するものです。
- 効果を確認しながら、個々の症例(特に併存疾患の有無)に応じて段階的にデエスカレーション(漸減・中止)を行うのが、引き続き現実的な戦略と言えます(追跡期間中の有害事象は13%、新規SPT開始は7例)。
参考文献
- Fofi L, Altamura C, Marcosano M, et al. The clinical outcome of patients starting monoclonal antibodies anti-CGRP with concomitant migraine preventive treatments. Cephalalgia. 2025;45(10):3331024251378776. doi:10.1177/03331024251378776
PUBMED: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41105547/